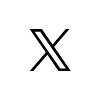コーポレートガバナンスコードのみならず、令和元年改正会社法においても上場会社等が社外取締役を置くことが義務付けられる(会社法327条の2)等、社外取締役等の独立役員への注目は益々高まっている。
本記事では、注目が高まる社外取締役と同じく、独立役員である社外監査役に弁護士が就任することの意義と留意点について若干の検討を行う。
弁護士を独立役員に招き入れる3つの意義section 01
社外取締役または社外監査役として弁護士を迎え入れることを検討する場合、会社としては既に顧問弁護士がいることが通常であろう。それでは、外部から独立役員の選任を求められているから、という消極的な理由ではなく、顧問弁護士がいる会社が、自社の事業に役立てるため、新たな弁護士を社外取締役または社外監査役として迎え入れる積極的な理由はあるといえるのであろうか。
(1)ガバナンスの強化
1点目として、独立役員の選任が会社に求める場合、少なくともその理由の1つはガバナンスの強化にあることからすれば、法令や各種規則等を遵守する体制を整えるという点で、法律の専門家である弁護士を招き入れることは合理性があるといえよう。
また、弁護士は外部専門家として多数の会社のガバナンス強化のサポートをしていることから、これらのサポートを通じて得られた知見や相場観を(守秘義務に反しない限りにおいて)自社に還元することができるという点も有益なポイントといえよう。
(2)ビジネスモデルの問題点や成長に必要な打ち手を得られる
2点目として、自社のビジネスモデル・業界に必要な知見を補うことが挙げられよう。例えば、AIに関する事業を営む場合、個人情報を含む各種情報やデータの処理の実務に長けた弁護士や、著作権や特許権を活用した知財戦略に長けた弁護士を独立役員として招き入れることで、自社が気付いていない問題点や、成長のために必要な打ち手を掘り起こしてくれることが考えられる。
特定の分野の専門の弁護士を探す場合、その弁護士の所属事務所・執筆歴・講演歴・受賞歴等を参考にすることも有益であろう。なお、これらの問題点や打ち手を踏まえた具体的な実務については、独立役員の立場上、当該役員自ら行うべきではない場合も少なくないと考えられるため、必要に応じて適切な他の弁護士を紹介してもらうことも有益であろう。
ある分野の専門家であれば、当該分野で活躍している同業の弁護士を人となりを含めて知っている可能性が高いので、自社に適した弁護士を紹介してもらえる可能性も高いだろう。
(3)既存業務の監査という役割
また、既に特定の弁護士に依頼している場合であっても、弁護士である独立役員に、既に依頼済の弁護士の業務等の監査を依頼することも有益であろう(その分野の専門家の方がその分野における仕事ぶりを適切に評価できる可能性が高いため)。
独立社外役員として弁護士を招き入れる際の留意点section 02
独立役員は、顧問弁護士とは異なり、独立役員としての職務執行について、会社だけではなく、株主や第三者に対して責任を負いうる立場にあり、また、内部の役員または従業員に比して会社の実情に疎くなりがちであるため、保守的な判断・発言をしがちなおそれがある。
特に、独立役員は、経営に関する議論にキャッチアップすることを前提に、独立した立場から、経営の適法性や妥当性[1]について意見を述べる必要があるが、経営に関する経験が不足しがちな弁護士が、会社の経営に関する議論をタイムリーに理解し、的確な意見を出すことは容易ではない。
そのため、(時には厳しいブレーキをかける必要があることは前提として)法令等の遵守について過度に保守的な意見ばかりを述べて、事業成長のお荷物になってしまうことは回避する必要がある。そのために、会社としては、以下の特性を持った弁護士を選任することが考えられよう。
<独立役員として選任すべき弁護士の特性>
- 自社のビジネスモデル・業界についての理解が深い(またはビジネスモデルを理解するための勉強や議論を厭わない)こと
- 自身の発言(特にブレーキをかける場合)が事業に与える良い影響と悪い影響を真に理解し、ブレーキをかける場合にも悪影響を最小限にとどめるにはどうすべきかも考えてくれる可能性が高いため
- 自社の成長フェーズに即した助言等が期待できること[2]
- 大企業と上場前後のスタートアップ[3]では独立役員に求められる役割や能力・姿勢等が異なると考えられるため
- 経営に関する議論に慣れている(または議論を好む)こと
- 法令違反等を発見した場合においても、それをいかに解消していくかについて、経営陣とビジネスを踏まえた建設的な議論をできる可能性が高いため
- 自社の成長に貢献するための監督をしてくれること
- 上述のように、保守的な判断・発言をしがちな状況にはあるので、(違法なことを見過ごすという意味ではなく、必要なブレーキはかけつつも)自社の成長を考えた上で必要な助言をしてくれること[4]
弁護士を独立役員として選任すべきタイミングsection 03
例えば上場を目指すスタートアップの場合、証券会社、東証や投資家等から独立役員の選任を求められて初めて独立役員候補者を探し、選考活動に入るというスタートアップも珍しくない。
可能な限り早い選任が必要
しかし、独立役員として人気の弁護士は市場に数少ない上、既に数社の独立役員を兼任し、新たに独立役員に就任することが不可能な状態にある場合も多く、自社の独立役員としての適性を有しており、かつ、自社が望むタイミングで独立役員に就任可能な弁護士を見つけるまでには、長い時間を要することも少なくない(上場準備中のスタートアップ間で社外取締役の争奪戦が起きている状態となっている[5])。
上場予備軍500社、社外取締役の争奪戦
指針強化で対応急務 人気人材は2年待ちも
年間の上場社数は90社前後で推移する。VCのボンズ・インベストメント・グループ(BIG、旧オプトベンチャーズ、東京・渋谷)の日野太樹パートナーは「500~600社が上場の準備をしているはずで、社外取人材の取り合いになっている」と指摘する。背景には上場予備軍の増加がある。ベンチャーエンタープライズセンターによれば、国内のスタートアップへの投資件数は19年度に1490件と、4年前から5割増えた。投資側は数年での上場での回収を目指し、投資先が社外役員を確保することは重要な要素だ。
引用元:朝日新聞|上場予備軍500社、社外取締役の争奪戦
また、自社の状況やカルチャーを理解した上で独立役員に就任した方が、ミスマッチも減り、当該独立役員がより良いパフォーマンスを発揮できる可能性が高くなるといえるところ。できる限り早い段階から、顧問弁護士とは別に、独立役員候補者を探し、単発での依頼等を通じて、コミュニケーションをとっていくことが有益であろう。
外部指摘の前段階から独立役員としての就任を
その際、独立役員の専任が必要と外部から指摘される前段階から独立役員として就任してもらい、実際の独立役員としての業務を通じて、(会社としても当該独立役員としても)会社と独立役員としてのコミュニケーションに慣れていくことで、独立役員が必要とされるフェーズでの業務をより円滑に進めていく(スタートダッシュを成功させる)ことも検討に値しよう。
また、早期に弁護士に独立役員を就任させた場合には、より早い段階で問題の掘り起こしに成功する可能性が高まるところ、人間の病気と同じく、一般的には、問題点はその発見が早ければ早いほど、その解決のための対応策の選択肢が増え、解決の可能性を高めることにつながるというメリットもある。
以上より、外部から独立役員の選任を求められてから検討するのではなく、できる限り早い段階から、
- 独立役員にいかなる点でいかなる役割を期待するかを検討し、
- 上記2で述べたような点に留意しつつ、これに適した弁護士を探し、
- 就任前からコミュニケーションをとり、自社への適性を図りながら、
- 必要に応じて早めに独立役員に就任させる
ことが有益といえよう。
顧問弁護士を社外取締役に選任する可否についてsection 04
(1)顧問弁護士が独立性を担保するか否かの議論について
顧問弁護士が社外性の要件を満たすかという問題については、様々議論がなされている。東京証券取引所は、「独立役員の確保に係る実務上の留意事項(2020年2月改訂版)」(以下「本留意事項」という。)[1]において、「上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)」については独立性に疑義があると示しつつ、顧問弁護士については、
「本項に該当し得る場合としては、顧問弁護士等が考えられますが、顧問弁護士であれば必ず『多額の金銭その他の財産を得ている』者に該当するというわけではありません。」
と示している。そのため、いかなる場合であれば、「役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」といえるかが問題となるものの、本留意事項は、
「『多額の金銭その他の財産』に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ニ又は同第76条第4項第6号二の『多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)』に準じて上場会社が判断するものとします。」
とするのみで、具体的な基準は明らかとなっていない。また、会社法においては、社外取締役または監査役に顧問弁護士が就任することの可否については、次のとおり議論がある。
(2)会社法における社外取締役または監査役に顧問弁護士が就任することの可否
社外取締役について、会社法2条15号にその定義が定められているが、顧問弁護士の社外取締役就任の可否との関係では、顧問弁護士が当該株式会社の「使用人」といえるか否かが問題となる。また、(社外)監査役への就任との関係では、監査役の独立性を求める会社法335条2項が兼任を禁止する「使用人」に顧問弁護士が該当するか否かが問題となる。顧問弁護士がこれらの「使用人」に該当するか否かについては、様々な見解[2]がある。
これらの議論について、共通する点を挙げるとするならば、顧問弁護士が社外役員への就任を検討している株式会社に従属的な立場と評価できるか否か、そして従属的と評価できるか否かを判断するにあたっては、これまでの報酬額の多寡等を考慮するというところであろう。
そのため、顧問弁護士が社外役員に就任することは一律には禁止されてはいないものの、就任を検討する場合には、報酬額等を考慮して、当該顧問弁護士は当該株式会社に従属的にはなっていないと十分に説明することができるかを慎重に検討する必要があろう[3]。
- [2] 例えば、日弁連は、会社の顧問弁護士は独立した業務をしており、使用人ではなく、顧問弁護士が当該会社の監査役を兼任することは旧商法276条(注:現会社法335条2項に対応。)には抵触しない、ただし兼任することの妥当性については慎重に配慮せよとの立場をとっている。他方で、法務省は、民事局4課の回答で、顧問弁護士も旧商法276条の「使用人」に該当すると解しており、「会社の顧問弁護士である者をその会社の監査役に選任する場合には、監査役就任の承諾を得る際に、顧問契約を解除しておくのが相当である」と示している。
- [3] 場合によっては、社外役員就任前に顧問契約を解除することも考えられよう。
結論:顧問弁護士は社外役員の候補として敬遠するべき
以上の議論を踏まえれば、顧問弁護士は社外役員の候補として敬遠するべきともいえよう。なお、顧問弁護士が自社にとって頼もしい存在であればあるほど、社外役員に就任させることにはためらいも出てくる。すなわち、顧問弁護士が社外役員に就任する場合、顧問契約を維持していたとしても、上述のように顧問弁護士としての報酬が多額になってしまうと社外性に疑義が生じてしまうため、必然的に相談量を減らさざるを得ないことになってしまうからである。
顧問弁護士が社外役員に就任するメリットもあるsection 05
他方で、顧問弁護士が社外役員に就任することのメリットもある。
顧問弁護士は、顧問契約を締結してからの期間の長短にもよるが、当該会社の(少なくとも法務や知財面の)実情に通じており、会社の実情を踏まえた問題点の洗い出しや、現実的な対応策の検討が期待できるというメリットもある。
そのため、上記(1)及び本項第1段落で述べたリスクと前段落で述べたメリットを天秤にかけつつ、顧問弁護士を社外役員に就任させるべきか否かを検討することとなろう。
- [1] 社外監査役が妥当性監査まですべきか否かという点については議論がある。ただし、取締役による著しく妥当性を欠く決定等は、善管注意義務(会社法330条、民法644条)違反を構成するため、社外監査役であっても一定程度は妥当性監査を行うべきといえよう。
- [2] 自社のフェーズにあったサポートが可能か否かについては、その弁護士の所属事務所・執筆歴・講演歴・受賞歴・独立役員を務めている(または務めていた)会社のフェーズ等を参考にすることも有益であろう。
- [3] 上場前後のスタートアップの場合は、上場準備実務のサポート経験のある弁護士を選ぶという視点も有益であろう。
- [4] 例えばルールメイキングや知財戦略等、経営陣を交えて、ビジネスをいかに進めるか・成長させるかという点を踏まえた議論が必要となる業務の経験が豊富か否か等も参考になろう。