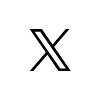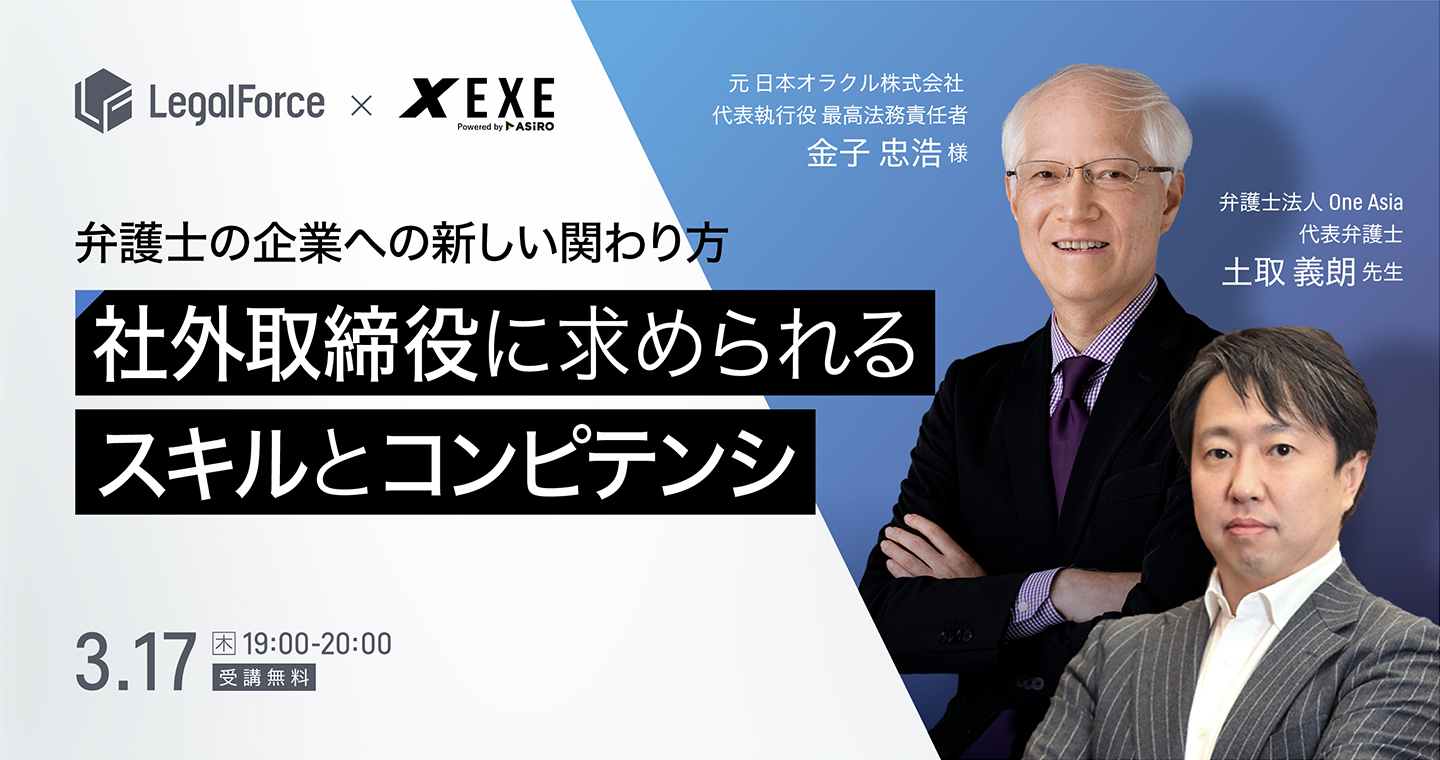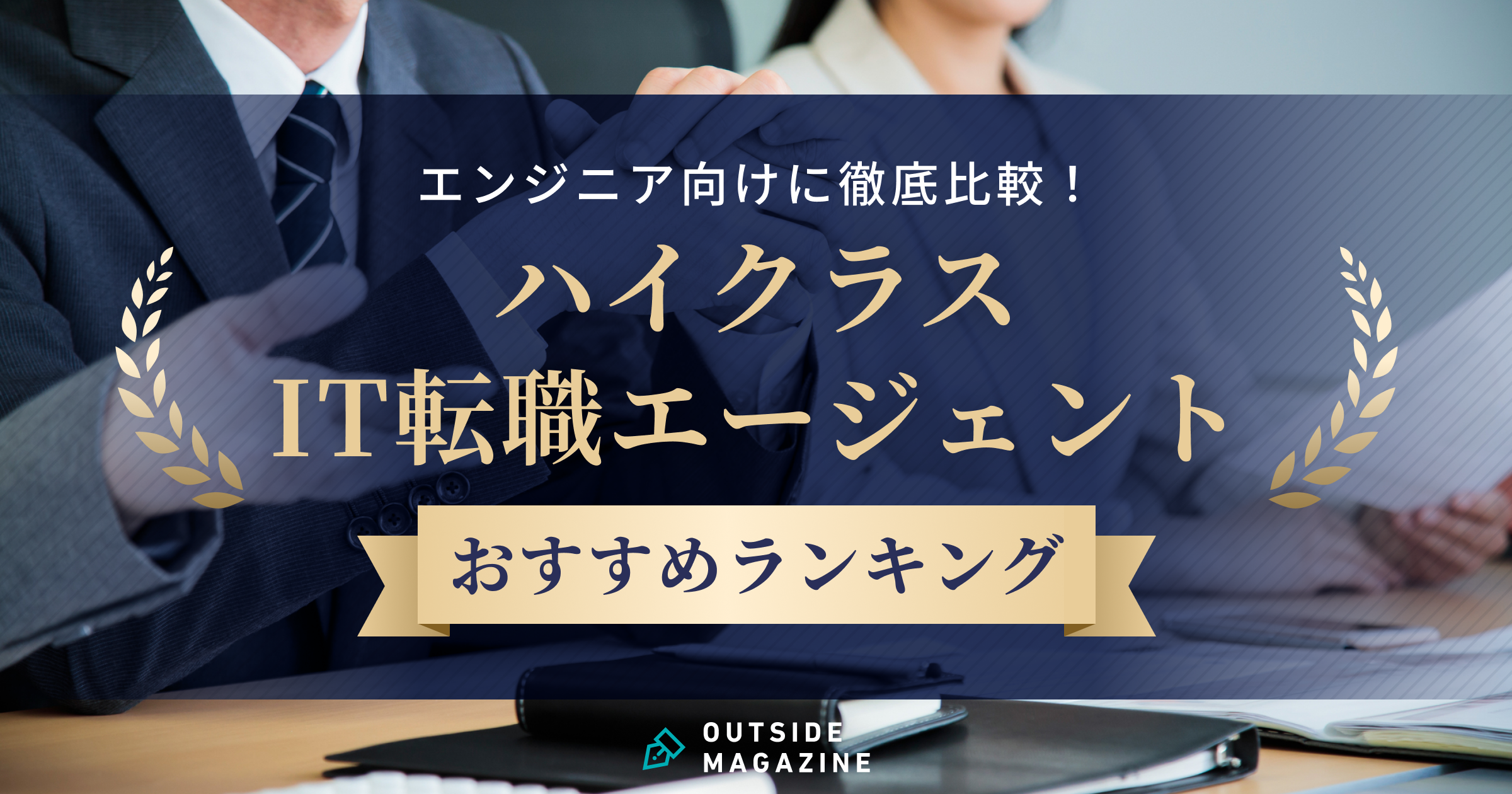「企業内弁護士ならワークライフバランスが取れる!」そんな話を聞いて企業内弁護士に興味を持った方も多いでしょう。
企業勤めで社会保険にも加入でき、福利厚生も十分に活用できるはず、そして週休2日は確保されている企業内弁護士は、ワークライフバランスを取るには最適であるというイメージが先行しますが、実際にどうなのか気になる人は多いでしょう。
本記事では、法律事務所と企業内弁護士の両方を知る弁護士が、企業内弁護士のワークライフバランスのリアルをお伝えします。
転職を検討している弁護士の方、すでに企業内弁護士として働いている方、そして法務キャリアに興味がある方にとって、記事が1つの参考となれば幸いです。
企業内弁護士はワークライフバランスが取りやすい?
企業内弁護士のワークライフバランスは雇用契約という構造の中で一定担保されますが、何をどの程度重視するかによっても定義が異なります。
結論から言えば、企業内弁護士のワークライフバランスは法律事務所と比較すれば、明確に立て分けやすいという観点から、プライベート時間を確保しやすい点でワークライフバランスをとりやすいといえます。
この差が生まれる最大の理由は、業務の予測可能性にあります。
法律事務所では、クライアントの突発的な依頼や訴訟の期日に振り回されることが日常茶飯事でした。金曜日の夕方に「月曜日までに契約書を完成させてほしい」という依頼が飛び込んでくることも珍しくありません。
一方、企業内弁護士の場合、社内の事業計画に沿って業務が進むほか、ある程度のスケジュール管理が可能です。もちろん緊急案件はゼロではありませんが、社内調整によって対応できるケースが少なくありません。
特に、雇用契約において週休2日制が整っているのが基本で、働き方改革の推進により残業規制が厳しくなっていることや、今年2025年の育児介護休業法改正により特に育児面での会社の配慮のあり方が大きく変わりました。
男性の育休取得も向上してきており、時短勤務、始業時刻変更、企業内保育所等の設置拡大などが今後進展していくでしょう。
ただし、これはあくまで一般論であり、企業規模や業界、役職によって状況は大きく変わります。後述しますが、ベンチャー企業の一人法務やCLOクラスになると、また話は別です。
【企業規模別】企業内弁護士の働き方
次に、企業内弁護士の特徴について、企業規模ごとに比較をしていきます。
大手企業の法務部
従業員1,000名以上の大手企業では、法務機能が高度に組織化されています。
法務も10数名以上の人員がいる場合もあり、業務領域ごとの専門チーム制、明確な権限委譲ルール、充実した研修制度などが整備され、予測可能性の高い働き方が実現しやすいでしょう。
組織構造
大手企業の法務部門では、一般的に契約法務、訴訟・紛争対応、コンプライアンス・内部統制、M&A・企業再編、知的財産などの機能別に業務が分かれています。
各分野には専任の担当者が配置され、明確な役割分担がなされているケースが多いです。法務部門の規模は企業によって大きく異なりますが、東証プライム上場企業では5〜30名程度の体制を持つ企業が一般的になります。
労働時間
業種・企業規模によって幅がありますが、大手企業では労働時間管理が比較的厳格に行われている傾向です。
大手企業の企業内弁護士の残業時間は、発生する場合月10〜40時間程度が標準的ですが、残業時間がほとんど発生しない場合もあります。法律事務所と比較すると、年間の総労働時間は20〜30%程度少ないのが肌感覚です。
制度面
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によれば、従業員1,000人以上の企業における年次有給休暇取得率は約65%に達しています。300人以上の規模感の会社でも、平均が61.8%という取得率となっており、増加傾向にあります。
リモートワーク制度については、総務省「令和5年通信利用動向調査」によれば、従業員数が1000人以上の規模感の企業であれば、テレワーク導入率は約75%に達しています。法務部門は業務の性質上、オンラインでの対応が可能な業務が多く、リモートワークを許容している企業が増加傾向にあります。
フレックスタイム制度も、大手企業では広く導入されており、コアタイム(10〜15時など)を設定した上で、始業・終業時刻を柔軟に設定できる環境が整いつつあります。
育児・介護支援については、育児・介護休業法の法定基準に加え、多くの大手企業が独自の支援制度を設けているケースも。時短勤務の対象年齢を小学校3年生まで延長したり、ベビーシッター補助(月3〜5万円程度)、病児保育補助などを提供する企業も増えています。
キャリアパスと報酬
法律事務所のパートナー弁護士(年収2,000万円以上のケースも多い)と比較すると報酬水準は低めですが、一般社員でも年収600万円程度が最低水準で、役職が付けば1,000万円前後に至ることもしばしばみられます。
福利厚生(住宅手当、退職金制度、各種補助等)を含めた実質的な待遇では、総合的に遜色ないケースも多いです。
また、労働時間を考慮した時給換算では、企業内弁護士の方が高くなる場合もあります。
メガベンチャー・IPO前後
従業員500〜3,000名規模のメガベンチャーやIPO前後の成長企業は、大手企業とスタートアップの中間的な特徴を持ちます。近年、特に働き方の柔軟性で、法務職種間では注目を集めている環境です。
組織構造
法務部門は5〜15名程度の規模で、大手企業ほど細分化されていませんが、主要領域(契約法務、コンプライアンス、上場準備など)ごとの担当制が敷かれています。
IPO準備企業では、証券会社や監査法人との調整業務が増加するため、一時的に体制が強化される傾向です。
ただ、IPOを迎えているような場合でも、法務はアウトソーシングしていたり、内製化が十分でない場合もあり、一人法務など極めて少人数の体制で運用している場合もあります。
労働時間
実務経験上、平時の残業時間は月30〜50時間程度ですが、IPO準備期間(申請前6ヶ月〜上場まで)は月60〜80時間まで増加するケースが見られます。
ただし、上場後は安定し、月40時間程度に落ち着くことが多いです。
制度面
メガベンチャーの最大の特徴は、働き方の柔軟性でしょう。
総務省「令和5年通信利用動向調査」によれば、情報通信業でのテレワーク実施率は他業種と比較して高く、フルリモート・フルフレックスを採用する企業も増えています。出社義務を月1〜2回のチーム会議のみとする企業も見られ、通勤時間の削減や、個人の生活リズムに合わせた働き方が実現しやすいです。
特にIT・テック系メガベンチャーでは、Slack、Notion、Zoomなどのコラボレーションツールを活用した非同期コミュニケーションが定着しています。
これにより、時差を活用した柔軟な勤務が可能となり、早朝型や夜型など、個人の特性に応じた働き方を選択できる環境が整うでしょう。
報酬とキャリアパス
年収水準は大手企業と同等かやや高く、500〜1,000万円(入社時)、1,000〜1,500万円(マネージャー)が多く見受けられます。加えて、ストックオプションが付与されるケースが多く、上場時に大きなキャピタルゲインを得られる可能性があるでしょう。
キャリア形成の観点では、IPOプロセスや急成長企業での法務経験は市場価値を高めます。3〜5年の経験を経て、より大手企業や専門性の高いポジションに転職するケースが多いです。
成長フェーズのベンチャー・スタートアップ
従業員50〜200名規模の成長フェーズのベンチャー・スタートアップは、企業内弁護士にとって最もチャレンジングな環境です。一方で、多様な経験と大きな裁量を得られる魅力もあります。
組織構造
法務担当が1〜2名という「一人法務」体制が一般的です。法務担当がいない場合もあり、業務委託による外注や、営業部のアシスタントで契約業務を担う場合もあります。
少人数であるがゆえ、契約書レビューから訴訟対応、知財戦略、資金調達の法務デューデリジェンス、労務問題まで、全ての法務業務をこなすことになるでしょう。
労働時間
資金調達ラウンド中や新規事業立ち上げ期には月60時間を超えるような残業が発生する場合がある一方、安定期には月10〜50時間程度に落ち着きます。予測可能性が低い点が、ワークライフバランス確保の最大の課題となるでしょう。
制度面
働き方の設計における自由度は極めて高くなっています。リモートワークの頻度、勤務時間帯、ツール選定など、多くの事項を自らの判断で決定できます。
「週4日リモートワークにしたい」「朝6時から働いて15時に終業したい」といった提案が即座に受け入れられる機動力があります。
また、法務戦略そのものを自ら構築できる点も大きな魅力です。
どのリーガルテックツールを導入するか、どの外部法律事務所と提携するか、契約書レビューのプロセスをどう設計するか—これら全てを主体的に決定できます。
もっとも、経営陣による法務やリーガルテックに対する感度や解像度にもよるため、法務予算を握れることや交渉力も必要です。
報酬とキャリアパス
転職サイトの公開求人情報によれば、年収は600〜900万円程度が中心ですが、それより低い300万円から500万円程度の待遇の場合も散見されます。大手企業よりは明らかに低い傾向があります。
ストックオプションが付与されるケースが多いですが、未上場企業の場合、実質的な価値は不確実です。
福利厚生も最低限の内容にとどまり、リモートワーク環境の整備費用などは自己負担となるケースもあります。
ただし、企業の成長スピードや人事評価制度の充実度によっては、短期間で大きく収入が上がったりボーナスが格段に高く付与されることもあります。
【役職別】企業内弁護士の特徴
次に、企業内弁護士の特徴について、役職ごとにみていきましょう。
法務担当レベル
法務部に配属された一般社員レベル(入社1〜3年目)は、企業内弁護士のキャリアにおいて基礎を形成する重要な時期です。ワークライフバランスの観点では、最も安定した働き方が可能な段階といえます。
業務内容
主な業務は定型的な契約書レビュー、簡易な法律相談対応、社内規程の整備支援などです。
重要案件や複雑な法的判断は上司が担当するため、業務範囲が明確で予測可能性が高い環境となります。月間の契約書レビュー件数は20〜40件程度が標準的です。
労働時間
一般社員の平均残業時間は月20〜40時間程度です。実務経験上、19時までに退社できる日が週3〜4日、20時までに退社できる日がほぼ毎日という状況が多く見られます。
繁忙期でも月50時間を超えることは少なく、安定した働き方が実現しやすくなるでしょう。
制度利用
リモートワーク制度は週1〜2日の利用が一般的です。
上位職と比較すると頻度は低いですが、これは業務習得のため出社を推奨される側面もあります。有給休暇取得率は70〜80%で、連続5日以上の休暇も年1〜2回取得できるケースが多いです。
スキル開発
企業法務の基礎スキル習得が主です。契約書の読み方、リスク判断の基準、社内調整の方法など、実務を通じて学習します。多くの企業では、OJTに加えて外部研修への参加機会(年2〜4回程度)が提供されます。
報酬
担当者クラスだと、年収は600〜800万円が中心です。
法律事務所のアソシエイト弁護士(800〜1,200万円)と比較すると低いですが、労働時間を考慮した時給換算では同等かそれ以上になるケースも多くなっています。
キャリア展望
3年程度の経験を積むことで、より高度な業務を担当するリーダー職への昇進が見込まれます。この時期に確実に基礎スキルを習得することが、長期的なキャリア形成の鍵です。
法務リーダー・課長
法務リーダーや課長クラスは、実務のプロフェッショナルとして最も活躍する段階です。専門性と責任が増す一方、ワークライフバランスの維持には戦略的アプローチが必要となります。
業務内容
高度な法的判断、部下のマネジメント(通常3〜5名)、経営層への報告、外部法律事務所との折衝などが主な役割となります。契約書レビューでは最終承認者として機能し、重要案件の法的戦略立案も担当します。業務においても、裁量の幅が広がってくるようなポジションです。
また、部下の育成、業務配分の調整、評価面談など、マネジメント業務が加わります。
労働時間
平均残業時間は月30~40時間程度で、一般社員時代より20〜30%程度長い傾向です。特に期末・期初、株主総会前、M&A案件進行中などの繁忙期には月45時間を超えることもあります。
一方、働き方の裁量は大きくなる傾向です。リモートワーク頻度(週2〜3日)、勤務時間帯の調整、業務優先順位の設定などを自ら決定しやすくまります。
制度利用
有給休暇取得率はやや低下する傾向があるのが肌感覚です。これは責任の増大により、長期休暇を取りにくくなる心理的要因が働くことが影響しています。
ただし、計画的に業務調整を行い、年1回程度の連続休暇(7〜10日)を取得することもできるでしょう。
報酬
転職サイトの公開求人情報によれば、年収は700〜1,200万円が標準的です。業績連動型のボーナスを導入する企業では、法務部門の貢献度(契約トラブル削減率、コンプライアンス研修実施率など)に応じて変動します。
キャリア展望
この段階で、専門性を深めるスペシャリスト路線か、経営に近づくマネージャー路線かの選択を迫られることが多いです。前者は技術的専門性を追求し、後者は組織マネジメント能力を高める方向性となります。
法務部長・統括
法務部長や統括のポジションがあるのは、従業員規模が300名を超えてくるような成熟したベンチャー企業ないし大企業で、100人前後のベンチャー・スタートアップ企業では、このレイヤーのポジションがおかれていることは少ないでしょう。
業務内容
法務戦略の立案、経営会議への参加、取締役会への報告、重要案件の最終判断、外部ステークホルダーとの関係構築などが主な職務です。実務的な契約書レビューからは離れ、戦略的・組織的な業務が中心となります。
週次または月次の経営会議への参加が定常化し、CEO・CFOとの直接的なコミュニケーションが多い傾向です。法務的観点から事業戦略にインプットを行い、場合によっては戦略の修正を提言する役割を担います。
そして、部長職の重要な責務として、次世代リーダーの育成も任されます。
労働時間
多くの企業では裁量労働制または管理職扱いとなり、残業代の概念がなくなります。労働時間は実質的に無制限ですが、完全に自己管理に任されるでしょう。実務経験上、週50〜60時間程度の勤務が一般的ですが、個人差が極めて大きくなっています。
重要なのは「時間」ではなく「エネルギー配分」です。経営会議、重要交渉、危機対応などの高負荷業務と、ルーティン業務のバランスを自ら設計する能力が求められます。
制度利用
平日夜間や週末の一部を仕事に充てる一方、平日日中に個人的な予定を入れる、長期休暇を取得するなど、独自のバランスを構築する事例が多く見られます。
この段階では、「労働時間の削減」ではなく、「質の高い時間の確保」がテーマです。
報酬
年収は1,000〜2,000万円が標準的で、一部の大手企業では2,000万円を超えるケースもあります。業績連動型の報酬制度を採用する企業が増えており、全社業績や法務部門のKPI達成度に応じて変動しる場合もあるでしょう。
CLOなど役員クラス
CLO(Chief Legal Officer)、GC(General Counsel)、または取締役(法務担当)などの役員クラスは、企業内弁護士のキャリアの頂点です。この段階では、「ワークライフバランス」という概念自体が従来の意味を持たなくなります。
業務内容
法務戦略の策定のみならず、全社戦略への参画、コーポレートガバナンスの設計、危機管理の統括、社外取締役・監査役との連携など、企業経営そのものに関与します。
大手企業では、法務部門に加えてコンプライアンス、内部監査、リスク管理などを統括する「チーフ・リーガル・アンド・コンプライアンス・オフィサー」として機能するケースもあるでしょう。
労働時間
取締役としての善管注意義務を負うため、24時間365日、企業の法的リスクに対する責任を持つ必要があります。緊急時(重大コンプライアンス違反、訴訟、M&A交渉など)には、深夜・休日を問わず対応が発生するケースも。
ただし、日常的な業務は高度に委譲されているため、平時の労働時間は部長職より短い場合もあります。実務経験上、週40時間程度の勤務でありながら、そのうち相当な時間を戦略的思考に充てているケースも見られます。
制度利用
役員クラスには、究極の時間的自由があります。
フレックス勤務制度を活用して平日昼間にゴルフや会食に行く、有給休暇を利用して1ヶ月のバカンスを取る、リモート制度を利用して海外の別荘で働くなど、理論上は全て可能です。
実際、グローバル企業のCLOの中には、年間の3分の1を海外で過ごすケースもあります。
しかし、責任の重さから、実際にそうする人は少数派です。「自由はあるが、使わない自由」という逆説的な状況が生じることも少なくありません。
報酬
年収は1,200万円から、大手企業では5,000万円を超えるケースもあります。ストックオプション、業績連動型報酬の比率が高く、全報酬の50〜70%を占めることも。
企業内弁護士のある一日
例として、企業内弁護士としての私のある一日についてご紹介していきます。
午前中
【9:15】出勤
まずはメールチェックとその日のToDoについて優先順位付けを行います。前日に行っておきますが、朝の他部署の動きや緊急度の高い案件が発生している場合があるため、始業時にチェックします。
【9:30~10:30】法務相談対応①
優先度に合わせて、各部署からの法務相談対応をします。主に、詳細なリサーチなどが不要なものから処理することでタイムパフォーマンスを上げる工夫をしています。また、チャットではなく口頭でのやり取りが議論の往復の時間を縮めることにつながる場合は、ハドルミーティングで解消します。
【11:00~11:30】プロジェクト関連のMTG
社内で進行しているプロジェクトに、法務担当者として参加している件の会議に参加しています。
【11:30~12:15】 契約書レビュー3件
午後に入る前に、軽微な作業を終わらせます。
午後
【13:30~15:00】 部署内定例ミーティングと経営会議に向けた資料作成
所属部署の定例ミーティングと経営会議で報告や議論をするための資料を作成します。所属部署は法務単体の部署ではないため、1つのチームとして参加します。経営会議では、リーガルリスクの検討が必要な案件について報告と論点整理、それを踏まえたディスカッションのファシリテートのため準備をします。
【15:00~15:30】部署内の定例ミーティング
【16:00~17:00】経営会議
夕方から夜
【17:00~17:30】直近の定例役会の製本作業
【17:30~18:15】法務相談対応②
午後に溜まった各部署の法務相談に対して打ち返しをします。
【18:15~18:55】重要案件の論点整理と検討
AIでリサーチをしながら、内容をまとめます。この辺りの作業も、普通であれば2時間半はかかりますが、AI活用により40分程度で代替終わらせることができるようになっています。
【18:55~19:00】次の日の業務整理
【19:00】退勤
いかがでしょうか?かなり細かいスケジュールであるのと、これは少しタイトなスケジュールを一例として取り上げました。
企業内弁護士のワークライフバランスのとり方4選
企業内弁護士のワークライフバランスの取り方は、企業の規模感、フェーズ、法務組織の体制や職務内容によって異なりますが、どのようにワークライフバランスを取ることができるのか、主な視点を解説していきます。
リモートワーク制度の活用
リモートワークは、企業内弁護士のワークライフバランス実現において最も効果的な施策の一つです。コロナ禍を契機に急速に普及し、現在では多くの企業内弁護士が何らかの形でリモートワークを活用しています。
導入状況のデータ
前掲の総務省「令和5年通信利用動向調査」によれば、企業規模別のテレワーク導入率は、従業員300人以上の企業で約80%、100〜299人で約60%となっています。特に情報通信業では導入率が高く、法務部門も業務の性質上、オンラインでの対応が可能な業務が多いため、積極的に導入されている傾向です。
生産性への影響
実務経験から、リモートワークによる生産性への影響は業務内容によって異なります。契約書レビューや法的リサーチなど、集中力を要する業務については、静かな環境で作業できるリモートワークの方が効率的です。
一方、対面でのコミュニケーションが必要な業務(複雑な案件の議論、若手育成など)では、出社の方が効率的な場合もあります。このため、ハイブリッド型(週2〜3日リモート、1~2日出社)が最適解であるという感覚です。
時間効率の改善
リモートワークの最大のメリットは通勤時間の削減です。
国土交通省「令和3年全国都市交通特性調査」によれば、東京圏の平均通勤時間は片道約40分となっています。往復で約80分、週3日のリモートワークで月間約16時間(年間約190時間)が節約される計算です。
この時間を家族との交流、自己啓発、休息に充てることで、生活の質が向上するでしょう。
また、柔軟な時間設定が可能となる点も重要です。「子どもを学校に送った後、8時30分から業務開始」「16時に一旦中断して子どもの迎え、20時から1時間だけ海外案件対応」といった働き方が実現できます。
有給休暇の取得
有給休暇の計画的取得は、ワークライフバランスの基盤となる施策です。
しかし、制度があっても取得率が低い企業は依然として存在し、組織文化の変革が課題となっています。
効果的な休暇取得には、年度初めの計画立案が重要です。年間カレンダーに主要な繁忙期(株主総会前、決算期など)をマークし、閑散期に休暇を配置します。
特に、連続5営業日以上の「リフレッシュ休暇」を年1〜2回設定することで、完全なリセットが可能となります。
これには個人の努力だけでなく、組織全体で休暇取得を推進する文化が重要です。管理職が率先して休暇を取ることで、部下も取得しやすい雰囲気が生まれます。
2019年の労働基準法改正により、年5日の有給休暇取得が使用者の義務となりました。
これを機に、多くの企業で取得促進の取り組みが強化され、年間休暇取得率を部門目標に設定し、達成状況を四半期ごとに確認している事例が見られます。
休暇取得予定表をチーム内で共有し、相互にカバーし合う体制を構築することも有効です。
メンバーが順番に休暇を取得し、お互いに業務をカバーする循環を作ることで、誰もが安心して休める環境が整います。
ほかにも、2021年の育児・介護休業法改正により、時間単位の有給休暇制度が普及しました。
これを活用すれば、半日や数時間の柔軟な取得も可能です。「午前中は子どもの授業参観に参加し、午後から出社」といった働き方が実現できます。
時短勤務の活用
時短勤務制度は、育児や介護などのライフイベントに対応する重要な施策です。企業内弁護士の場合、専門職としての高い生産性により、時短勤務でも十分な成果を出せるケースが多くなっています。
利用状況
育児・介護休業法に基づき、3歳未満の子を養育する労働者には1日6時間の短時間勤務が保障されています。多くの企業では、これを上回る独自制度を設けており、小学校3年生まで、あるいは小学校卒業までの時短勤務を認める例が増えています。
生産性維持の工夫
時短勤務で成果を出すには、業務の優先順位付けと効率化が必須です。
まず、定型業務の徹底的な効率化です。契約書レビューはテンプレートとチェックリストで標準化し、1件あたりの処理時間を削減します。また、リーガルテックツールを最大限活用し、AIによる初期レビューを経た契約書のみを人間がチェックする体制とします。
次に、重要業務への集中です。定型的な業務は他のメンバーに委譲するか、システム化することで、自身の関与を最小化します。
チーム体制での支援
時短勤務者がいる場合、業務配分の見直しが必要です。私も実務経験上、16時以降に発生する緊急案件は他のメンバーが対応し、翌朝に引き継ぐルールを確立しています。
重要なのは、時短勤務を「個人の問題」ではなく「チームで支える体制」と位置づけることです。
育児期間は通常3〜8年程度で、その後はフルタイムに戻るケースが多くなっています。長期的視点で見れば、優秀な人材を組織に留めることの価値は、一時的な業務調整のコストを遥かに上回る傾向です。
シッター利用などの子育て補助
子育て支援制度、特にベビーシッター補助や病児保育補助は、ワークライフバランスと業務継続を両立させる重要な施策です。近年、こうした制度を導入・拡充する企業が増加しています。
制度の種類と内容
主な子育て支援制度として、以下が挙げられます。
①ベビーシッター補助:民間シッターサービス利用時の費用を補助するものです。月額3〜5万円、利用料の50〜70%を企業が負担する形があります。
②病児保育補助:子どもの急な発熱時に利用する病児保育サービスの費用補助です。
③ベビーシッターの社内常駐:企業内または近隣に託児施設を設置し、社員が利用できる体制で、いわゆる企業内保育所です。大手企業での導入が進んでいます。
④学童保育補助:小学生の放課後預かりサービスの費用補助です。導入企業が多いわけではありませんが、こうした補助も有効であると考えられます。
利用実態と効果
実務経験上、子育て中の企業内弁護士がこれらの制度を活用しています。
例えば、週2回ベビーシッターに子どもの保育園送迎と夕食準備を依頼することで、夫婦ともに18時まで安心して働ける環境を整えているケースがあります。私自身も、ベビーシッターの活用により、育児・家事の負担を軽減できるようにしています。
経営的合理性
企業側にとっても、子育て支援制度は合理的な投資です。優秀な法務人材を育児離職させずに定着させることで、採用・育成コストを削減できます。
また、ワークライフバランスの良好さが採用ブランディングにも寄与します。
企業内と事務所勤務でのワークライフバランス比較
企業内弁護士と法律事務所勤務の場合、ワークライフバランスはどの程度差があるでしょうか。
休みの取りやすさ
法律事務所と企業内弁護士では、休暇取得のしやすさに構造的な差異が存在します。この差は、ビジネスモデルの違いに起因するものであり、個別企業の方針を超えた本質的な特徴です。
法律事務所
法律事務所のビジネスモデルは「時間チャージ制」または「成功報酬制」が基本です。弁護士の労働時間が直接的に収益に結びつくため、休暇取得は機会損失と認識されやすい構造があります。
実務経験上、法律事務所勤務弁護士の有給休暇取得率は30〜50%程度にとどまるケースが多く見られます。ほとんどないケースもゼロではありません。特にアソシエイト弁護士(勤務弁護士)の場合、クライアント対応が優先されるため、計画的な休暇取得が困難となります。
訴訟案件を抱える場合、裁判期日の前後は休めません。M&A案件では、クロージング直前に数週間連続で深夜まで働くことも珍しくありません。このような予測不可能性が、プライベートの予定を立てにくくする最大の要因です。
さらには、法律事務所の勤務弁護士の場合、基本的にはパートナーや業務委託であるため、労働基準法に関する枠組みが当てはまらない(当てはめることが不都合)性質があります。
企業内弁護士
一方、前掲の厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によれば、企業全体の有給休暇取得率は62.1%です。実務経験上、企業内弁護士の場合、これを上回る70〜80%程度の取得率を実現しているケースが多く見られます。
このような差が生じる要因は複数あります。
第一に、業務の予測可能性です。社内の事業計画やプロジェクトスケジュールは事前に把握できるため、繁忙期を避けて休暇を計画できます。株主総会後の7〜9月、決算後の5月などは比較的余裕があり、連続休暇を取得しやすいです。
第二に、チーム体制によるカバーです。複数名の法務担当がいる企業では、相互に業務を引き継げる仕組みが整備されています。休暇取得者の業務を他のメンバーが分担し、復帰後は逆にカバーする循環が機能します。
第三に、労働法規の遵守意識です。企業は労働基準法の適用を受ける当事者として、有給休暇取得を推進する立場にあります。2019年の法改正による年5日の有給休暇取得義務の遵守はもちろん、それを上回る取得を奨励する企業が多いです。
定時退勤
定時退勤の可能性は、ワークライフバランスを測る最も直接的な指標の一つです。法律事務所と企業内弁護士では、この点でも顕著な差異が見られます。
法律事務所
法律事務所における定時退勤は、極めて困難です。実務経験上、法律事務所勤務弁護士で定時(18時と仮定)に退勤できる日が週1日以下というケースは珍しくありません。
この背景には、クライアント主導のスケジュールがあります。
「金曜日の17時に依頼を受け、月曜日の朝までに契約書を完成させる」といった無理な納期が常態化している事務所も存在します。また、訴訟案件では準備書面の提出期限が厳格に定められており、期日前は深夜・休日の作業が不可避です。
さらに、長時間働くことが美徳とする組織文化も影響しています。若手が定時で帰ろうとすると、やる気がないと見なされるケースすらあり、こうした環境では、自身の予定を優先することが心理的に難しいです。
企業内弁護士
企業内弁護士は、実務経験上で週3日以上定時退勤できるケースは相当数に上ると考えられます。
平均的な退勤時刻は18〜19時で、19時以降まで残る日は週2〜3日程度です。22時を超える残業は、M&A案件や重大コンプライアンス事案などの例外的な状況に限られます。
この実現を可能にする要因は複数あります。
第一に、社内業務は緊急性が相対的に低いことです。「今日中に」という依頼も、実際には「明日の朝まで」で対応可能なケースが多くなっています。
第二に、業務の標準化と効率化が進んでいることです。定型的な契約書レビューはテンプレート化され、短時間で処理できます。
第三に、労働時間管理が厳格であることです。36協定の遵守はもちろん、過重労働防止の観点から、管理職が部下の退勤時刻を把握し、長時間労働者には注意喚起する体制が整っています。
福利厚生の充実度
福利厚生の充実度も、法律事務所と企業内弁護士で大きな格差が存在する領域です。この差は、報酬面での比較以上に、実質的な生活水準に影響を与えます。
法律事務所
法律事務所、特に中小規模の事務所では、福利厚生は最低限の法定福利(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)にとどまるケースが多くなっています。実務経験上、法定外福利厚生を提供する法律事務所は限定的です。
- 住宅手当:導入している事務所は少数派
- 家族手当:導入している事務所は少数派
- 退職金制度:導入している事務所は一部、ただし勤続3年以上が条件のケースも
- 健康診断:法定の定期健診のみ(人間ドック補助は少ない)
- 育児支援:ほとんど提供されていない(ベビーシッター補助等は稀)
大手法律事務所(パートナー50名以上)では状況はやや改善しますが、それでも一般企業と比較すると見劣りすることが多いです。
これは、法律事務所のビジネスモデルが「高報酬・低福利厚生」を前提としているためです。弁護士は高い報酬を得て、自ら必要な福利を購入するという考え方が背景にあります。
企業内弁護士
企業内弁護士は雇用企業の福利厚生制度をフルに享受できるでしょう。特に大手企業では、包括的な福利厚生パッケージが提供される場合があります。
考えられる主な福利厚生の内容は以下の通りです。
①住宅関連
- 住宅手当:月3〜7万円(企業規模により異なる)
- 社宅・寮制度:大手企業で提供される例あり
- 住宅ローン補助:金利優遇制度を設ける企業も
②家族関連
- 家族手当:配偶者月5千〜2万円、子ども1人あたり月5千〜1.5万円
- 出産祝い金:企業により10〜30万円程度
- 育児支援:ベビーシッター補助(月3〜5万円)、病児保育補助などを提供する企業も
③健康関連
- 人間ドック:年1回、会社全額負担する企業も
- メンタルヘルス支援:カウンセリング制度を設ける企業も
- フィットネス補助:スポーツジム補助を提供する企業も
④資産形成
- 退職金制度:確定給付年金または確定拠出年金、勤続年数に応じて支給
- 財形貯蓄:給与天引き制度
- 持株会:従業員持株制度を設ける企業も
⑤その他
- 食事補助:社員食堂や食事手当を提供する企業も
- 通勤手当:全額支給が一般的
- 資格取得支援:外部研修費用補助を提供する企業も
- リフレッシュ休暇:勤続年数に応じて特別休暇を付与する企業も
金銭換算での比較
これらの福利厚生を金銭換算すると、相当な額となります。実務経験上、年間で数十万円から100万円以上の価値がある場合も珍しくありません。
例えば、年収1,000万円の企業内弁護士の場合、福利厚生を含めた実質的な待遇は1,100万円前後相当となるケースもあります。
一方、法律事務所で年収1,200万円を得ていても、福利厚生がほとんどない場合、実質的には同等かそれ以下の待遇となる可能性があります。
特に子育て世帯では、この差が顕著です。
ベビーシッター補助、病児保育補助、育児時短勤務などを活用することで、年間数十万円相当の経済的メリットを享受できます。
企業内弁護士でワークライフバランスを確保するための戦略
最後に、企業内弁護士で、さらにワークライフバランスを充実させるための戦略的な方策について、いくつか解説していきます。
業務効率化とリーガルテックの活用
企業内弁護士がワークライフバランスを実現するには、限られた時間で最大の成果を出す必要があります。そのための最も効果的な手段が、業務効率化とリーガルテックの活用です。
業務効率化の体系的アプローチ
効率化は場当たり的ではなく、体系的に取り組むべきです。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を法務業務に適用し、継続的改善を図ります。
第一段階は「業務の可視化」です。どの業務にどれだけの時間を費やしているかを、1週間〜1ヶ月単位で記録します。実務経験上、契約書レビュー40〜50%、法律相談対応20〜30%、会議10〜20%、その他10〜20%という配分が典型的です。
第二段階は「優先順位付け」です。アイゼンハワーマトリクス(重要度×緊急度)を用いて、各業務を分類します。「重要かつ緊急」な業務は自ら対応し、「重要だが緊急でない」業務は計画的に実施、「緊急だが重要でない」業務は委譲、「緊急でも重要でもない」業務は削減します。
第三段階は「標準化」です。反復的に発生する業務については、テンプレート、チェックリスト、マニュアルを整備します。実務経験上、秘密保持契約、取引基本契約、業務委託契約など主要な契約類型について標準フォーマットを作成することで、レビュー時間を30〜50%削減できるケースが見られます。
率先した福利厚生利用
ワークライフバランス実現の第二の戦略は、既存の福利厚生制度を率先して活用することです。特に管理職の立場では、自らが利用することで部下も使いやすい組織文化を醸成できます。
多くの企業で、福利厚生制度は整備されているものの、利用率が低いという課題があります。その背景には、「制度を使うと評価が下がる」「周囲に遠慮してしまう」といった心理的障壁が存在します。
実務経験上、福利厚生制度の存在を知りながら利用しない理由として、「周囲が使っていないから」「上司が良く思わないのではと心配」「キャリアに悪影響があるのでは」といった声が聞かれます。
この心理的障壁を打破するには、管理職が率先して制度を利用し、「使っても問題ない」というメッセージを発信することが極めて重要です。
経営層に法務人材の戦略を訴求する
ワークライフバランス実現の第三の戦略は、法務部門の戦略的重要性を経営層に訴求し、人的投資を引き出すことです。これは長期的かつ根本的な解決策といえます。
多くの企業で、法務部門は「コストセンター」と認識されています。契約書レビュー、訴訟対応など、必要だが直接的な収益を生まない機能として位置づけられがちです。
この認識を変えるには、法務部門の活動を定量的に可視化し、ビジネスへの貢献を明示する必要があります。
まとめ
企業内弁護士のワークライフバランスについて、多角的な分析を行ってきました。最後に、重要なポイントを総括します。
企業内弁護士のワークライフバランスは法律事務所と比較して優位であると考えられます。残業時間は20〜40%程度少なく、有給取得率は大幅に高く、定時退勤の機会も多くなっています。福利厚生を含めた実質的な待遇も、多くのケースで企業内弁護士が上回ります。
ただし、これらは傾向にすぎず、個別企業や役職によって状況は大きく異なります。大手企業の一般社員レベルでは非常に良好なワークライフバランスが実現可能である一方、ベンチャー企業の一人法務や役員クラスでは、相応の負荷が生じます。自身のライフステージとキャリア志向に応じた選択が重要です。
企業内弁護士であってもワークライフバランスの実現には、様々な工夫が必要です。
たとえば、①業務効率化とリーガルテックの活用、②率先した福利厚生利用、③経営層への法務人材戦略の訴求、という3つの戦略が有効です。
業務効率化とリーガルテック活用により、限られた時間で最大の成果を出すことが可能となります。率先した福利厚生利用により、組織文化を変革し、全メンバーがワークライフバランスを享受できる環境を整えられます。
そして、経営層への戦略的訴求により適正な人員配置と投資を引き出し、持続可能な法務組織を構築できます。