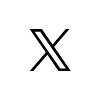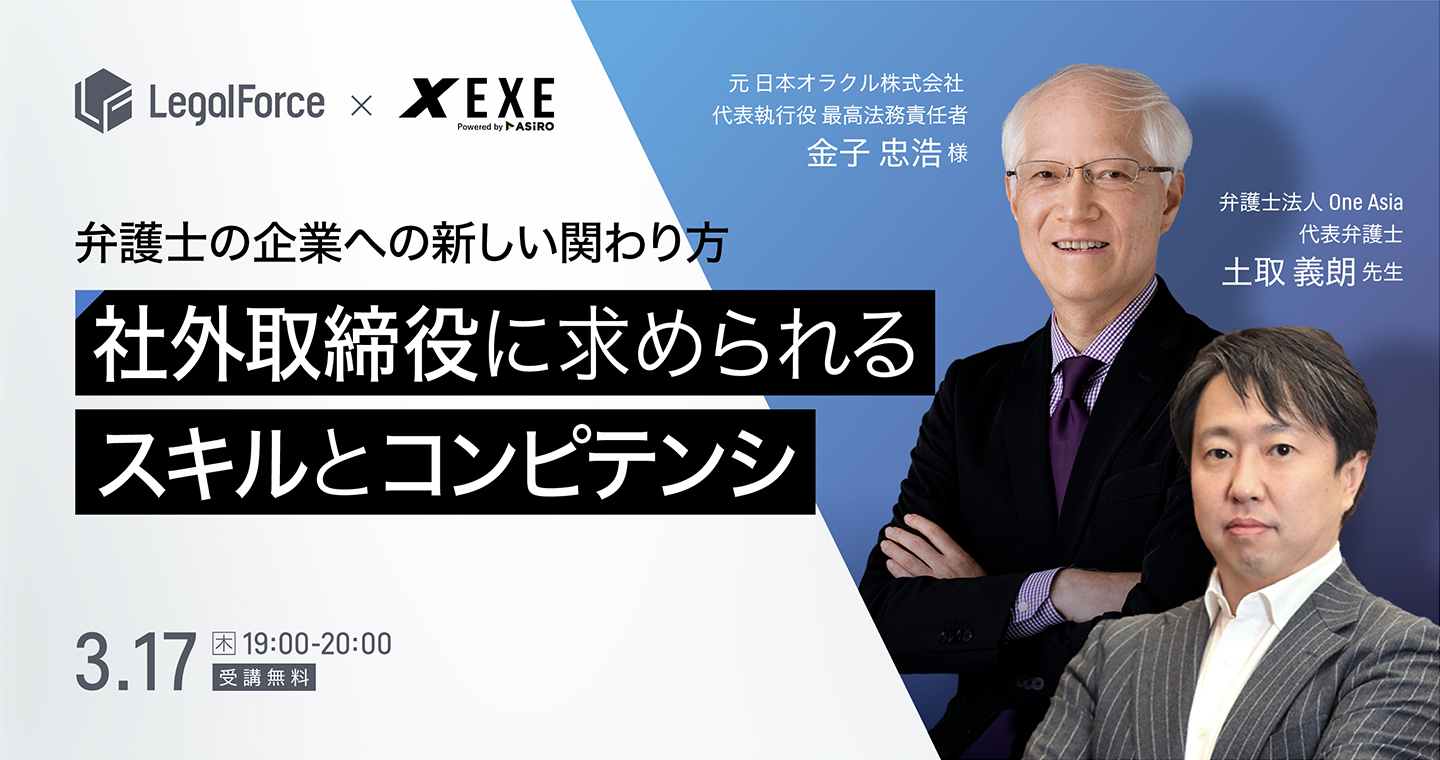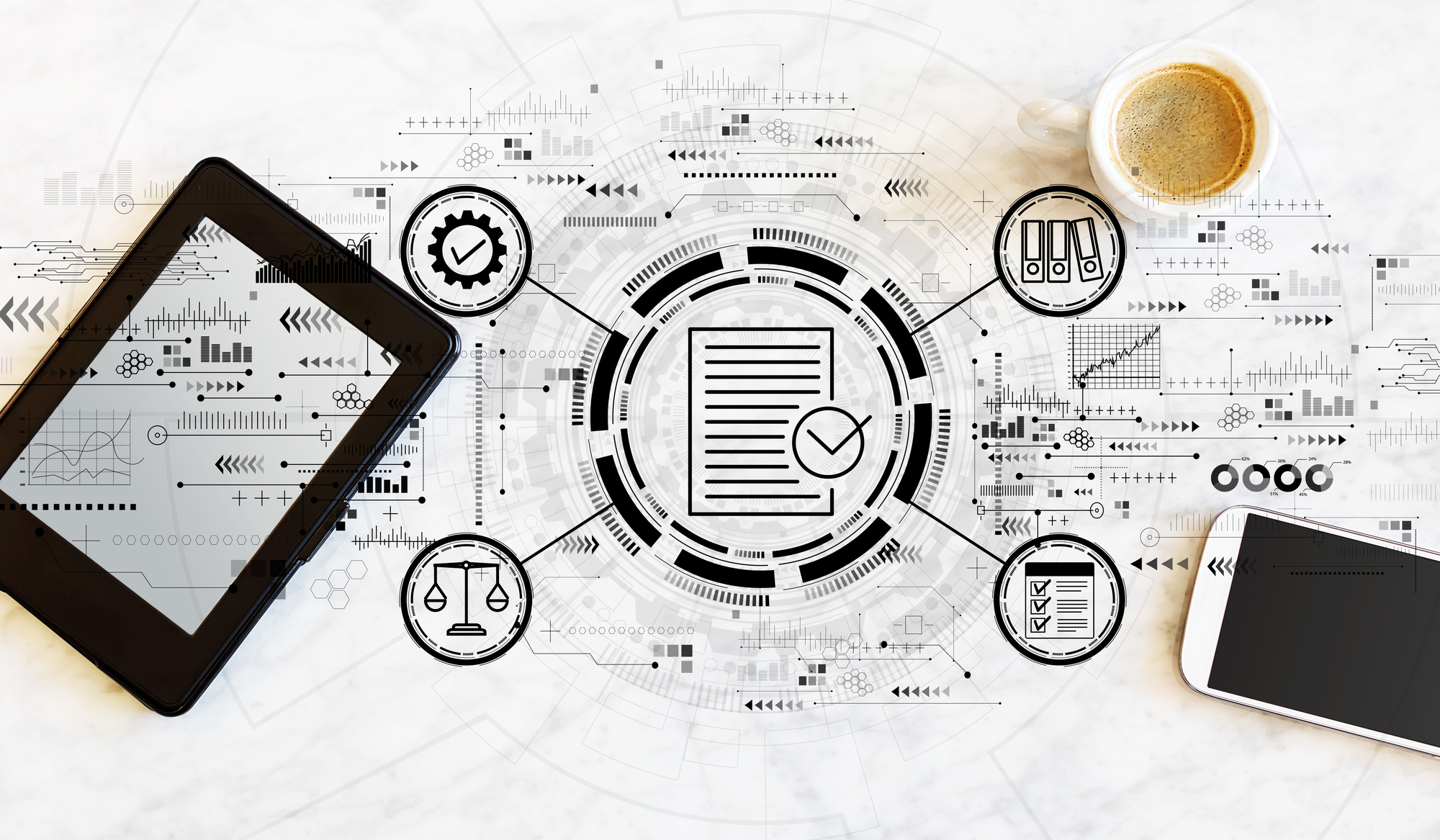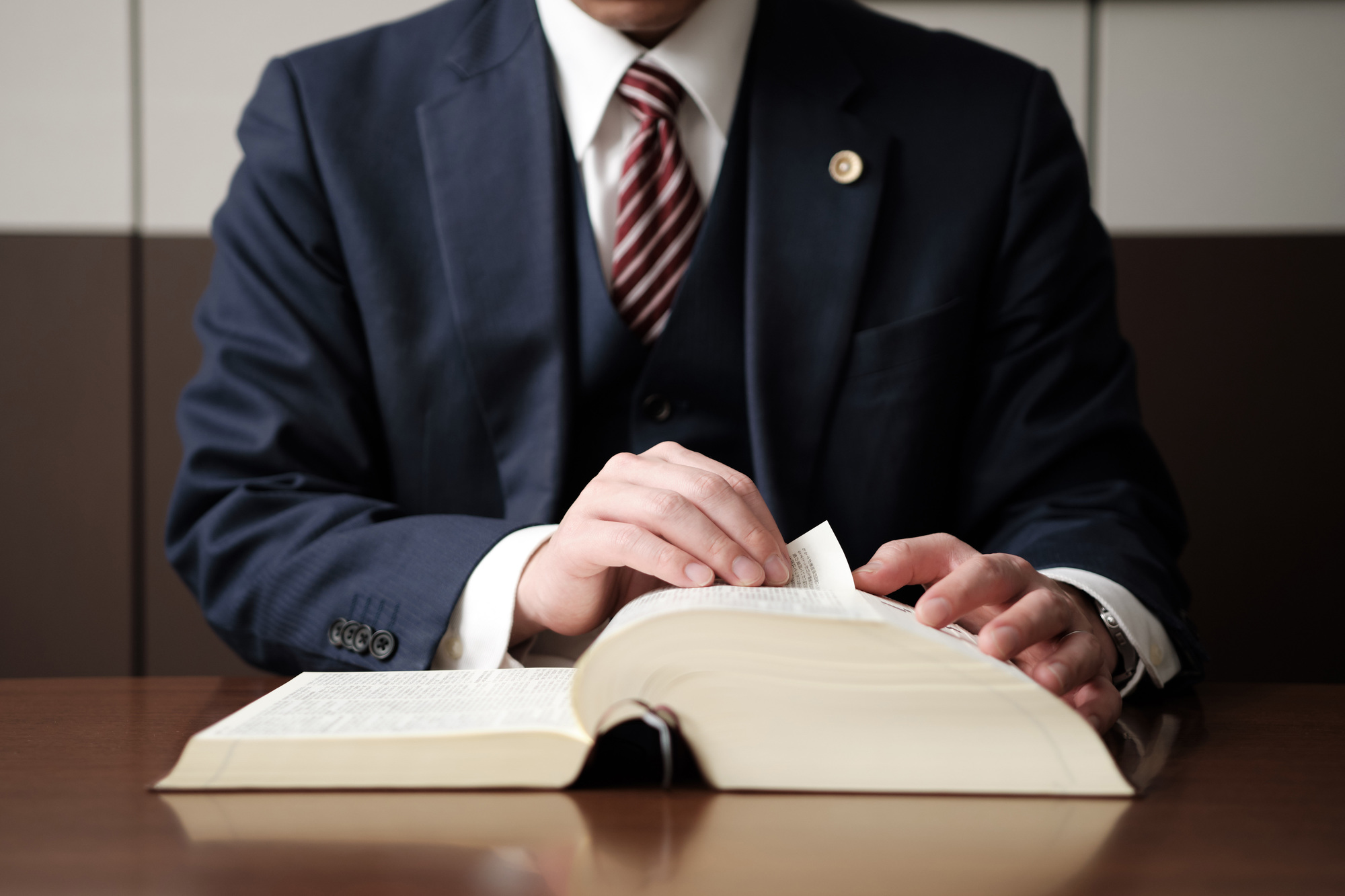企業がコンプライアンス違反を犯した場合、企業イメージの低下に加えて、対応にかかるコストや損害賠償請求などによって多額の損失が生じてしまいます。
コンプライアンス違反は、日々の業務のあらゆるところから発生する可能性があります。そのため、コンプライアンス違反のよくあるパターンを把握したうえで、自社のオペレーションに問題がないかを常にチェックし続ける体制を整えましょう。
この記事では、コンプライアンス違反のよくある事例・リスク・予防策・対処法などについて、企業の注意点を幅広く解説します。
コンプライアンスのよくある違反事例8つsection 01
企業はさまざまな法律によって規制されているため、常にコンプライアンス違反の危険にさらされています。実際に、企業において発生する可能性があるコンプライアンス違反には、非常に多くのパターンが存在します。以下では、よくあるコンプライアンス違反の事例の一部を紹介します。
品質偽装・産地偽装
食品の品質・産地などに関する表示については、食品表示法および食品表示基準によってルールが決まっています。たとえば、食品表示基準に従った表示を行わずに食品の販売をしたり、原産地について虚偽の表示をしたりする行為は罰則の対象とされています(食品表示法18条、19条)。
しかし、実際よりも良い印象を消費者に与えて誤導するため、品質偽装・産地偽装をするケースが見られることも事実です。品質偽装・産地偽装が判明すると、当事者が刑事罰に処される可能性があるうえ、消費者の企業に対する信頼は一挙に失墜してしまいます。
したがって、品質偽装や産地偽装は、重大なコンプライアンス違反と捉えるべきでしょう。
衛生管理の不備
食品の衛生管理については、食品衛生法により詳細な規律が定められています。しかし、食品の衛生管理状況は、生産者・加工者などの外部からは見えにくいのが実情です。
「どうせわからないのだから」とずさんな衛生管理を行い、実際に健康被害が発生したり、内部リークが行われたりして発覚するケースがしばしば発生します。食品衛生法に違反した不衛生な食品管理は罰則の対象とされているうえ、衛生管理の不備が判明した食品については、消費者の購買意欲は一挙に削がれてしまうでしょう。
そのため、食品に関する事業を営む事業者は、食品の衛生管理を徹底しなければなりません。
違法な労務管理
会社による従業員の雇用については、労働基準法・労働契約法その他の労働法令において、詳細なルールが定められています。特に時間外労働との関係では、労働基準法が正しく適用されず、適切に残業代が支払われないケースが多いです。
他にも不当解雇・ハラスメントの問題は、会社と従業員との間で深刻なトラブルを生じやすい傾向にあります。従業員との労務トラブルが発生してしまうと、会社としてはトラブル対応に大きな時間的・経済的コストを費やすことになります。
また、違法な労務管理が露見すれば、今後の採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。よって企業としては、労務管理に関するコンプライアンスを徹底し、従業員とのトラブルを回避するように努める必要があります。
個人情報や営業秘密などの不正流出
情報管理体制がずさんなために、メールの誤送信やハッキングなどにより、個人情報や営業秘密が流出するケースがあります。また、退職する従業員によって、営業秘密が持ち出されるケースもしばしば見受けられます。
機密情報の不正流出は、個人情報保護法やNDAへの違反に該当し、企業は罰則・行政処分・損害賠償などのペナルティを受ける可能性があります。特に営業秘密が流出した場合、自社のノウハウを他社に流用されるなどして、自社の売上に対して直接的なインパクトを生じるおそれが否定できません。
近年では、情報管理の重要性は社会的にも非常に強調されています。自社の利益を守ると同時に、企業が社会から非難されることを防ぐためにも、情報管理を徹底することが求められます。
他社の知的財産権の侵害
自社が他社の特許権・商標権・著作権などを侵害した場合、差止め(商品回収)や巨額の損害賠償を強いられる可能性があります。知的財産権の侵害が発生する原因は、多くの場合、新たなビジネスや製品開発を行う際に十分な事前調査を行わなかったことにあります。
知的財産権のデータベースなどを活用して、自社の製品やネーミングなどが他社の権利を侵害していないかをよく確認してから、製品の開発・販売へと着手することが大切です。
景品表示法違反
景品表示法では、いわゆる「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が禁止されています(景品表示法5条1号、2号)。
優良誤認表示
商品やサービスの品質・規格などの内容が、実際のものよりも著しく優良である、または同業他社のものよりも著しく優良であると示す表示を行うこと。
有利誤認表示
商品やサービスの価格などの取引条件が、実際のものよりも著しく有利である、または同業他社のものよりも著しく有利であると示す表示を行うこと消費者に対して商品やサービスを提供する際に、合理的な範囲でセールストークが行うことは、営業上問題ありません。
しかし、セールストークが行き過ぎてしまうと、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」として景品表示法違反に該当する可能性があるので注意が必要です。
「優良誤認表示」や「有利誤認表示」は、いわば「誇大広告」に当たり、長期的な視点では消費者からの信頼を失うことに繋がりかねません。そのため、現場レベルで不当な表示が行われていないかを、定期的にチェックすべきでしょう。
会社資産の公私混同・横領
会社の資産と経営者個人の資産は厳密に区別されるべきであり、この点は小規模な企業であっても同様です。経営者が会社資産を不正に横領した場合、株主からの信頼を失うほか、刑事罰に問われる可能性もあります。
さらに、債権者からの印象も非常に悪くなるため、運転資金の調達が困難になる事態も生じかねません。上記のリスクを防止するためには、経営陣相互の監視を強化するなどして、会社資産の公私混同・横領を防ぐ必要があります。
不正会計(粉飾決算)
不正な会計処理により脱税をしたり、粉飾決算をして自社の業績を良く見せかけたりする行為は、特別背任罪(会社法960条)その他の犯罪に該当します。
不正会計(粉飾決算)を行った経営者が逮捕・起訴される可能性はきわめて高く、株価の暴落も避けられないでしょう。会社が築き上げてきた信頼を一挙に失墜させないためにも、適切な会計監査を行い、公明正大な会計処理を心がけることが大切です。
なぜコンプライアンス違反がおきるのか?主な原因7つsection 01
コンプライアンス違反は、単一の原因ではなく、個人の意識から組織構造の問題まで、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。ここでは、その主要な原因を7つ挙げ、それぞれ専門的な視点から解説します。
知識・理解不足
コンプライアンス違反の最も基本的な原因の一つが、そもそも守るべき法令や社内規程を知らない、あるいはその内容や目的を正しく理解していないという点です。特に、法規制が複雑化・高度化する現代においては、自分たちの業務にどの法律が、どのように関わってくるのかを正確に把握することは容易ではありません。
専門的な観点から見ると、これは単なる「無知」の問題に留まりません。従業員が「自分には関係ない」「専門部署が対応すべきことだ」といった当事者意識の欠如に陥っているケースや、規程の文言を自己に都合よく解釈してしまう認知バイアスが働いているケースも多く見られます。
また、過去の慣習や前任者からの引き継ぎを無批判に踏襲し、その行為が現在の法令に抵触していることに気づかない「思考の停止」も典型的なパターンです。これを防ぐためには、単に規程を周知するだけでなく、その背景や目的、違反した場合のリスクを具体的に伝え、自分事として捉えさせる継続的な教育と、疑問点を気軽に相談できる風通しの良い環境を構築することが不可欠です。
過度なプレッシャーと目標達成への歪んだ動機
過大なノルマや達成困難な業績目標は、従業員を精神的に追い詰め、不正行為への引き金となる極めて重大な要因です。特に、短期的な利益や成果を過度に重視する組織では、従業員は「目標を達成するためなら、多少のルール違反は許される」という歪んだ考えに陥りがちです。
行動経済学における「プロスペクト理論」で説明されるように、人間は利益を得る喜びよりも、損失を回避する際の苦痛をより強く感じる傾向があります。
プロスペクト理論とは
不確実な状況下で人がどのように意思決定を行うかを説明した、行動経済学の非常に重要な理論です。一言でいうと、「人は利益を得る喜びよりも、同額の損失を被る苦痛の方をはるかに強く感じる」という、人間の感情的な側面を考慮した理論です。この理論は、伝統的な経済学が「人間は常に合理的に最大の利益を追求する」と考えるのに対し、「いや、人間はもっと感情的で、必ずしも合理的とは言えない判断をするよ」と指摘した点で画期的でした。
目標未達という「損失」を目前にしたとき、そのプレッシャーから逃れるために、コンプライアンス違反というハイリスクな選択肢に手を出してしまうのです。この状態では、長期的に会社の信頼を失うといった甚大なリスクよりも、目先の目標達成という短期的な利益が優先されてしまいます。
経営層は、現場の実態を無視した非現実的な目標が、いかに従業員の倫理観を麻痺させ、不正の温床となりうるかを深く認識し、結果だけでなくプロセスも公正に評価する健全な目標管理制度を設計・運用する必要があります。
不正を許容する組織風土と同調圧力
「みんなやっているから大丈夫」「上司の指示だから仕方ない」「この業界では当たり前だ」。こうした言葉が蔓延している組織では、コンプライアンス違反が常態化しやすくなります。個々の従業員に倫理観があったとしても、不正を容認・黙認する組織の文化や、周囲に合わせなければならないという強力な同調圧力が、その規範意識を上回ってしまうのです。
社会心理学でいう「集団浅慮(グループシンク)」の状態に陥ると、組織内では異論や反対意見が封じ込められ、集団にとって都合の良い結論が安易に導き出されます。不正行為が発覚しても、「見て見ぬふり」をする、あるいは問題提起した者が疎外されるような環境では、自浄作用は働きません。
このような組織風土は、一度根付くと変革が非常に困難です。小さな不正や倫理的でない行為を放置することが、より大きな違反行為への心理的なハードルを下げ、組織全体の規範意識を徐々に蝕んでいく「割れ窓理論」と同様の現象を引き起こします。
健全な組織風土の醸成には、経営トップの強いリーダーシップと、倫理的な行動を称賛し、非倫理的な行為には断固として対処するという一貫した姿勢が不可欠です。
経営層のコミットメント不足
コンプライアンス体制を構築する上で、最も重要な要素は経営トップの姿勢です。これを「トーン・アット・ザ・トップ」と呼びます。経営者がコンプライアンスを「コスト」や「事業の足かせ」と捉え、その重要性を軽視する言動を取れば、そのメッセージは即座に組織の末端まで伝わります。たとえ立派な行動規範や規程集が存在しても、経営層が本気で取り組んでいなければ、それは単なる「お題目」となり、従業員の意識や行動に結びつくことはありません。
経営層のコミットメント不足は、様々な形で現れます。例えば、コンプライアンス部門へのリソース(人員、予算)の配分を渋る、コンプライアンス違反が発覚した際に収益への影響を恐れて穏便に済ませようとする、利益を上げた社員の不正には寛容な態度を示す、といったケースです。
これらの態度は、従業員に対して「会社は利益さえ上がれば、コンプライアンスは二の次なのだ」という誤ったシグナルを送ることになります。真にコンプライアンスを組織に根付かせるためには、経営層が自らの言葉と行動で、いかなる状況においても倫理的・法的な正しさを優先する、という明確かつ一貫したメッセージを発信し続けることが絶対条件となります。
不十分な監督・牽制体制
不正行為が発生する背景には、それを行おうと思えばできてしまう「機会」が存在します。組織内部における監督機能や相互牽制の仕組みが不十分であると、この「機会」が生まれやすくなります。
例えば、特定の個人や部署に権限や業務が過度に集中している状態は非常に危険です。担当者一人の判断で重要な取引が完結してしまったり、経理と実務担当者が同一人物であったりする場合、不正を発見することが極めて困難になります。
内部統制のフレームワークである「三つの防衛線(The Three Lines of Defense)」モデルは、この問題への有効な示唆を与えます。すなわち、
- 業務を遂行する事業部門(第一線)
- リスク管理やコンプライアンスを担う専門部門(第二線)
- 独立した立場で監査を行う内部監査部門(第三線)
それぞれ適切に役割を果たし、相互に連携・牽制することで組織全体の防御力が高まります。また、内部通報制度が形骸化している、あるいは通報者が不利益を被るような運用がなされている場合も、不正の発見・是正の機会を失う深刻な欠陥と言えます。堅牢な監督・牽制体制の構築は、不正の「機会」そのものを減らすための物理的な防波堤となるのです。
結果至上主義の評価・報酬制度
従業員の行動は、組織が何を評価し、何に報いるかによって大きく方向づけられます。もし、企業の評価・報酬制度が売上や利益といった結果のみを重視し、その達成プロセスを問わないものであれば、それは「手段を選ばずに結果を出せ」というメッセージに他なりません。
このような結果至上主義の制度は、コンプライアンス違反を誘発する強力なインセンティブとして機能してしまいます。
例えば、短期的な業績目標の達成度のみでボーナスや昇進が決まる場合、従業員は長期的な会社の評判や顧客との信頼関係を犠牲にしてでも、不正な手段を用いて目先の数字を確保しようとするかもしれません。インセンティブ設計におけるこのような欠陥は、従業員の倫理観を歪め、組織全体を誤った方向へ導く危険性をはらんでいます。
これを防ぐためには、定量的な業績だけでなく、コンプライアンス遵守の姿勢や倫理的な行動といった定性的な側面も評価の対象に組み込むことが重要です。また、不正行為によって得られた成果に対しては報酬を与えない、あるいは厳格な処分を下すといったルールを明確に定め、公正なプロセスこそが最終的に評価されるという文化を醸成する必要があります。
個人の倫理観の欠如と「正当化」
組織的な要因に加え、最終的に不正行為に手を染めるのは個人の判断です。そして、その背景には個人の倫理観の欠如や、不正行為を自分の中で正当化してしまう心理的なメカニズムが存在します。犯罪学の分野で知られる「不正のトライアングル」理論は、不正が発生するための3つの要素として「動機」「機会」「正当化」を挙げています。ここで特に重要なのが「正当化」のプロセスです。
多くの不正行為者は、自らを「悪人」だとは考えていません。彼らは、「これは会社を救うために必要なことだ」「ライバルもやっていることで、業界の慣行にすぎない」「誰も具体的に傷つけているわけではない」といった、都合の良い理由付けをすることで自らの罪悪感を麻痺させ、不正行為への心理的抵抗を乗り越えてしまうのです。
この「正当化」は、個人の倫理観が低い場合に容易に行われるだけでなく、前述したような組織的なプレッシャーや不正を容認する風土によって助長されます。個人の倫理観だけに依存したコンプライアンス対策には限界があり、組織として不正を「正当化」させない明確な規範を示し、倫理的な判断に迷った際に相談できる仕組みを整えることが不可欠です。
コンプライアンス違反が発覚した場合の8つのリスクについてsection 02
コンプライアンス違反が発覚した場合、企業はさまざまな観点からダメージを被ってしまいます。そのため、コンプライアンス強化を「コスト」と厭わずに、誠実な取り組みを行うことが大切です。コンプライアンス違反によって企業に生じるリスクの例としては、主に以下のものが考えられます。
会社のブランドイメージが毀損される
会社が提供する商品やサービスについてコンプライアンス違反が発生した場合、直接関連する商品・サービスのイメージだけでなく、会社のブランドイメージ自体が毀損されてしまいます。
特にメディアの影響力が強い昨今では、ブランドイメージの毀損による売上・利益へのダメージは甚大です。関連商品を含めた売上の低下により、企業が多大なダメージを被ることを防ぐためにも、コンプライアンス違反を徹底して排除する必要があります。
クレーム対応に人員を割く必要がある
消費者向けの商品・サービスに関してコンプライアンス違反が発覚した場合、消費者からのクレームが殺到します。この場合、クレーム対応専門のチームを組織したうえで対応すべきケースも多く、人件費がかさんでしまうでしょう。さらに、クレーム対応に人材を割いた結果として、他の業務が人員不足でひっ迫するおそれもあります。
製品・食品の回収等に多大なコストがかかる
製品の不具合や食品の品質・産地偽装の場合、対象の製品・食品は回収を余儀なくされます。回収分については当然売上が立たないうえ、回収自体にもコストがかかるので、会社が被る損失は甚大な規模に及ぶでしょう。
訴訟などにより多額の損害賠償義務を負う可能性がある
コンプライアンス違反の内容によっては、消費者や他社から、多額の損害賠償請求を受ける可能性があります。たとえば、以下の場合などには、損害賠償の金額が高額になりやすい傾向にあります。
- 製品の不良や食品の衛生管理の不備などによって人身被害が生じた場合
- 他社の主力商品の特許権を侵害した場合
- 大規模な機密情報の流出が発生した場合
上記のコンプライアンス違反が発生した場合、会社にとっては予定外の出費を強いられることにより、経営が傾くおそれも否定できません。多額の損害賠償が発生する可能性のある業務領域については、特にコンプライアンス違反への警戒度を高めて対応する必要があるでしょう。
監督官庁から行政処分や行政指導を受けることがある
労務管理全般に関するコンプライアンス違反が発覚すると、労働基準監督署により、行政処分や行政指導が行われる可能性があります。また、会社の業種によっては、監督官庁(金融庁・厚生労働省など)からの監視が厳しく行われています。
もしコンプライアンス違反が発覚すれば、所轄の監督官庁から報告書の提出を求められたり、業務改善命令等の行政処分が行われたりする場合もあります。監督官庁への対応は多大な労力を要するうえ、措置を公表された場合には、社会的な信頼に対する悪影響も生じてしまうでしょう。
特に監督官庁から厳しく監視されている業種の事業主は、コンプライアンスに関する緊張感を常に保っておかなければなりません。
会社や経営者などに刑事罰が科されるおそれがある
会社内部で発生する違法行為の中には、犯罪として刑事罰の対象となるものも多いです。特に横領・脱税・粉飾決算などは重罪であり、当事者にはきわめて重い刑事罰が科される可能性があります。経営者が処罰された場合、会社のキーパーソンが欠け、さらに会社の信頼も失墜する深刻な事態になってしまうでしょう。
採用活動に悪影響が出て人材確保が困難になる
コンプライアンス違反を犯した企業は、社会的なイメージが低下することに伴い、新規採用・中途採用に苦戦することがよくあります。コンプライアンス違反による悪いイメージを払拭しない限り、優秀な人材を十分に確保できず、業績が右肩下がりになってしまうことも十分あり得るでしょう。
株価の暴落・株主からの信頼失墜
コンプライアンス違反は、株式市場にとっても強い悪印象を与えるので、上場企業であれば株価の暴落は避けられません。株価が低迷する状況が続くと、長期保有株主も会社を見放して株式を売却し、低水準の株価が定着してしまうおそれがあります。
コンプライアンス違反を予防するための対策6つsection 03
上記のようなコンプライアンス違反による弊害を防ぐためには、企業は以下の点に留意したうえで、コンプライアンス強化の取り組みを進めることが大切です。
社内で二重・三重のコンプライアンスチェックを行う
コンプライアンス違反を可能な限り排除するには、社内にダブルチェック・トリプルチェックの体制を整えることが有効です。基本的には顧客との取引を担当する現場レベルと、法務・経理などのバックオフィスレベルのそれぞれで、独立したコンプライアンスチェックの機構を備えておくのが望ましいでしょう。
さらに、社内に監査部門を設置して三重のチェック体制を設ければ、より万全に近づきます。
社外取締役を招聘してコンプライアンスチェック機能を強化する
経営陣による違法行為を防ぐためには、経営陣相互の監視を機能させることが重要です。会社からの独立性が高い社外取締役を招聘すれば、コンプライアンスの観点を含めて、経営陣の相互監視を強化することに繋がります。
特に弁護士など、コンプライアンスに関する見識が深い人材を社外取締役に登用すれば、いっそうコンプライアンスチェック機能が強化されるでしょう。
従業員に対するコンプライアンス研修を行う
会社全体としてコンプライアンスを強化するには、現場担当レベルの従業員を含めて、社内の全員がコンプライアンスへの意識を高めることが大切です。そのためには、従業員に対するコンプライアンス研修を行うことが、効果的になります。
コンプライアンス研修により、従業員のコンプライアンス意識が高まれば、現場レベルでのコンプライアンス違反の発生を抑止することに繋がるからです。コンプライアンス研修の講師は、法務・コンプライアンスに関する実務経験が豊富な弁護士などに依頼するとよいでしょう。
内部通報制度を導入する
公益通報者保護法に基づく内部通報制度では、従業員が社内の違法行為を通報した場合、通報の事実によって従業員が不利益に取り扱われないことが保障されています。内部通報制度を設けることにより、従業員による違法行為の通報が促され、コンプライアンス違反による深刻な損失を未然に防ぐことに繋がるでしょう。
なお、内部通報制度の実効性を確保するためには、社外窓口の設置が推奨されます。社外窓口の依頼先としては、会社からの独立性が確保された弁護士などが考えられます。
経営陣が自ら現場と積極的にコミュニケーションをとる
現場レベルでのコンプライアンス違反を防ぐためには、経営陣が現場で何が起こっているかをタイムリーに把握することが大切です。経営陣主導で現場との意思疎通を積極的に行い、小さなコンプライアンス違反の種を見逃さないようにしましょう。
弁護士のリーガルチェックを受けることも有効
会社内部だけでコンプライアンスチェックを行うのは、専門的知識やマンパワーの面から限界があります。この点を補うためには、外部弁護士によるリーガルチェックを受けることが有効です。弁護士と顧問契約を締結して、日常の業務の段階からこまめにリーガルチェックを受けることで、コンプライアンス違反のリスクを相当程度減らすことができるでしょう。
コンプライアンス違反が発生してしまった場合の対処法section 04
万が一コンプライアンス違反が発生してしまった場合、会社に生じる損失を最小限に食い止めるためには、適切な事後対応を行うことがきわめて重要です。コンプライアンス違反への事後対応を行う際には、主に経営陣が以下の各点に留意して、臨機応変に判断・行動してください。
迅速に事実関係を調査する
コンプライアンス違反への対応は、何よりもスピーディに行うことが肝心です。対応が遅れれば、被害の拡大・風評の拡散等によって、会社はより深刻なダメージを受けてしまうことになりかねません。
そのため、コンプライアンス違反への対応の前提となる事実関係の調査は、必要な人員を総動員して迅速に行うべきです。
プレスリリースなどでこまめに情報を発信する
コンプライアンス違反によって失墜しかけている社会の信頼を繋ぎとめるためには、透明性を持った対応をタイムリーに行うことが大切になります。コンプライアンス違反によって会社に失望していた人々も、事後対応に誠実さが感じられれば、会社を見直す可能性が高いです。
たとえばプレスリリースをまめに更新するなど、コンプライアンス違反への対応状況について、随時発信を続けるとよいでしょう。
製品・食品の回収は真っ先に行う
製品の不具合や食品の品質偽装・産地偽装などが判明した場合、対象となる製品や食品は真っ先に回収しなければなりません。万が一消費者に健康被害や事故などが生じてしまっては、危機管理の対応が手遅れになりかねません。
また、企業の評判への悪影響を防ぎ、迅速な対応をアピールする観点からも、製品・食品の回収は大いに急ぐべきです。事実関係の調査が完了していなくても、問題の拡大を防ぐためには、対象製品・食品を回収する優先度の方が高いと認識する必要があります。
必要に応じて取引先や監督官庁などへの報告を行う
自社にコンプライアンス違反が生じた場合、取引先は大きな不安を抱えている可能性が高いです。取引先に対して誠実に対応するという観点からは、早い段階で謝罪の連絡を入れるとともに、コンプライアンス違反への対応状況を随時連絡して不安解消に努めるべきでしょう。
また業種によっては、後の行政処分などを緩和する観点から、監督官庁への状況報告をタイムリーに行うことも重要です。自社のビジネスに対する規制内容や、監督官庁との関係性などを踏まえて、適切に対応を行いましょう。
自社のオペレーションを見直して再発防止に努める
一度コンプライアンス違反が発生してしまった場合、同じ違反が繰り返されないように、再発防止を徹底する必要があります。もしコンプライアンス違反の原因が判明したら、問題があった点を中心に、自社のオペレーションを抜本的に見直して再発防止に努めるべきでしょう。
コンプライアンス違反の原因分析や、再発防止策の検討を行う際には、弁護士などの有識者にアドバイスを求めることをお勧めいたします。
関係者を処分する際には労働法などの規制に注意
コンプライアンス違反に関与した役員・従業員に対して一定の処分を行う場合は、各種法令の規制に注意する必要があります。たとえば役員の解任は、株主総会決議によって行うことができます(会社法339条1項)。
これに対して、従業員を解雇する場合には、「解雇権濫用の法理」(労働契約法16条)によって制約がかかることに注意が必要です。安易に従業員を解雇すると、従業員から解雇の無効を主張されて、労働審判や訴訟などに発展する可能性があります。
会社にとって、労働審判や訴訟への対応はかなりの負担になるため、解雇処分の適否について事前の詳細な検討が不可欠です。
危機管理を得意とする弁護士への依頼が有効
コンプライアンス違反への危機管理対応は、スピード感を必要とするうえに、やるべきことが非常に多いという特徴があります。会社にとって経験したことのない大問題に発展する可能性もあることから、危機管理の専門家に相談するのがよいでしょう。
危機管理業務を得意とする弁護士に相談すれば、コンプライアンス違反発覚直後の対応から再発防止策に至るまで、ワンストップで対応を依頼できます。コンプライアンス違反によって、自社に生じる悪影響を最小限に食い止めるためにも、早い段階で弁護士への依頼をご検討ください。
コンプライアンスの違反を無くし強化するための施策5つsection 01
コンプライアンス強化は、規程の整備といった形式的な取り組みだけでなく、組織の隅々にまでその意識を浸透させ、実践的な仕組みを構築することが不可欠です。
顧問弁護士による「予防法務」の徹底活用
コンプライアンス強化の第一歩は、問題が発生してから対処する「臨床法務」ではなく、問題の発生を未然に防ぐ「予防法務」に軸足を置くことです。ここで極めて重要な役割を果たすのが、企業の内部事情にも精通した顧問弁護士です。
顧問弁護士の役割は、単に契約書をチェックするだけではありません。新規事業を開始する際のビジネスモデルの適法性チェック、広告表示が景品表示法や薬機法に抵触しないかのレビュー、個人情報保護法に準拠したデータ管理体制の構築支援など、事業のあらゆる場面で法的リスクを事前に洗い出し、その対策を講じることができます。
重要なのは、「何かあったら相談する」のではなく、「何かを始める前に必ず相談する」という文化を組織内に定着させることです。弁護士との定期的なミーティングを設定し、経営層や事業責任者が法的な視点を持つ機会を設けることで、組織全体の法的リスクに対する感度を高め、コンプライアンス違反の芽を早期に摘み取ることが可能になります。
内部通報制度の外部委託と実効性の確保
内部通報制度は、組織の自浄作用を機能させるための生命線ですが、社内の人間が窓口となっている場合、「通報したら報復されるのではないか」という不安から、制度が形骸化してしまうケースが少なくありません。そこで有効なのが、通報窓口を独立した第三者機関である法律事務所に外部委託することです。
弁護士には守秘義務が課せられており、通報者の匿名性を厳格に保護します。これにより、従業員は安心して不正の事実を報告できるようになります。さらに、法律事務所が窓口となることで、通報内容の事実関係の調査や法的評価を、中立的かつ専門的な立場から迅速に行うことができます。
調査の結果、重大なコンプライアンス違反が認められた場合には、取締役会への報告や是正勧告、再発防止策の策定支援までを一貫して任せることが可能です。
単に窓口を設置するだけでなく、通報後の調査プロセスや通報者保護のルールを明確にし、「通報することが会社への貢献になる」というポジティブな認識を従業員に浸透させることが、制度を実効的に機能させる鍵となります。
eラーニング・LMS(学習管理システム)を活用した継続的な教育
全従業員のコンプライアンス意識を底上げするためには、継続的かつ効率的な教育が不可欠です。ここで大きな力を発揮するのが、eラーニングやLMS(学習管理システム)といったITツールの導入です。
これらのツールを活用すれば、全従業員に対して、時間や場所を選ばずに均質な教育コンテンツを提供できます。例えば、ハラスメント防止、情報セキュリティ、インサイダー取引規制といった普遍的なテーマから、各部門の業務に特化した法令(建設業法、下請法など)まで、対象者に応じた多様な研修プログラムを設計できます。
LMSを導入すれば、誰がどの研修をいつ受講し、テストに合格したかといった学習履歴を一元管理でき、未受講者へのリマインドも自動化できます。これにより、教育担当者の負担を大幅に軽減しつつ、全社的な教育の徹底を図ることが可能になります。
重要なのは、一度研修を実施して終わりにするのではなく、法改正や社会情勢の変化に応じてコンテンツを定期的にアップデートし、反復学習を促す仕組みを構築することです。
契約書レビュー・管理システムの導入による業務効率化とリスク低減
企業の活動は契約によって成り立っており、契約書に潜むリスクを管理することはコンプライアンスの根幹です。しかし、事業規模の拡大に伴い、契約書の数は膨大になり、法務部門や担当者の手作業によるレビュー・管理には限界があります。
そこで有効なのが、AI(人工知能)を活用した契約書レビュー支援ツールや、契約書管理システムの導入です。
AI契約書レビューツールは、不利な条項や欠落している条項、法令に抵触する可能性のある文言などを瞬時に検出し、修正案を提示してくれます。これにより、法務担当者はより高度な判断が求められる業務に集中でき、レビューの品質向上と時間短縮を両立できます。
また、契約書管理システムを導入すれば、契約の締結日、更新日、終了日などを一元管理し、更新漏れや契約違反のリスクを自動で検知できます。電子契約サービスと連携させれば、契約締結プロセス全体の透明性を高め、内部統制を強化することも可能です。これらのツールは、ヒューマンエラーを減らし、属人化しがちな契約管理業務を標準化するための強力な武器となります。
コンプライアンス・チェックリストのデジタル化とモニタリング
日々の業務の中にコンプライアンス遵守のプロセスを組み込むためには、具体的な行動指針となるチェックリストが有効です。そして、その運用を確実なものにするためには、チェックリストをデジタル化し、ワークフローシステムなどに組み込むことが推奨されます。
例えば、新規取引先の選定時に「反社会的勢力との関係がないか」「許認可は取得しているか」といった項目をデジタルチェックリスト化し、承認フローに組み込むことで、担当者の確認漏れを防ぎます。
また、個人情報を取り扱う業務では、取得時の同意確認から廃棄プロセスまでの一連の流れをチェックリスト化し、実施記録をシステム上に残すことで、説明責任を果たすための証跡を確保できます。
重要なのは、これらのチェック結果を定期的にモニタリングし、傾向を分析することです。特定の部署でチェック漏れが頻発している、あるいは特定の項目で「No」が続くといった傾向が見られれば、それは組織的な弱点や潜在的なリスクを示唆しています。データに基づいたモニタリングによって、より的を絞った改善策を講じることが可能になるのです。
まとめ
企業は日常的にコンプライアンス違反のリスクに晒されており、一度コンプライアンス違反が生じると、甚大な損失を被ることにもなりかねません。そのため、企業全体としてコンプライアンスへの意識を高めるとともに、社内のチェック体制を強化して違反の予防に努めることが大切です。
万が一コンプライアンス違反が発覚した場合には、公明正大かつ迅速な事後対応が肝要になります。
コンプライアンス違反による企業への悪影響を最小限に食い止めるためには、リスク管理の実務に長けた弁護士に依頼して、対応策を協議することをお勧めいたします。コンプライアンスを強化して違反を予防したい、またはコンプライアンス違反に直面して対応が必要な企業経営者・担当者の方は、お早めに弁護士までご相談ください。