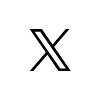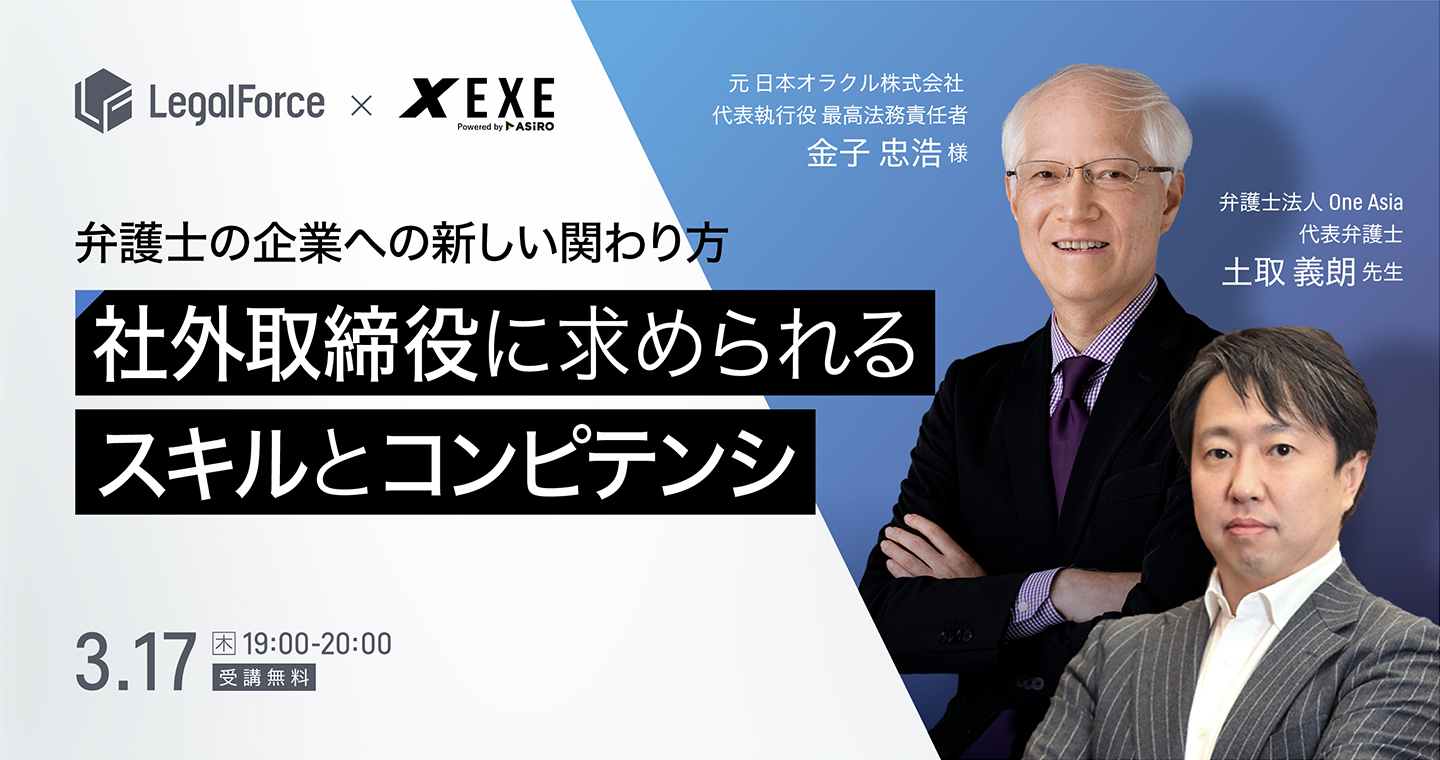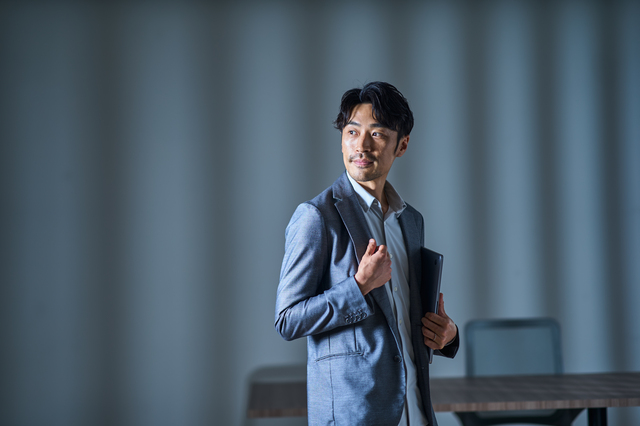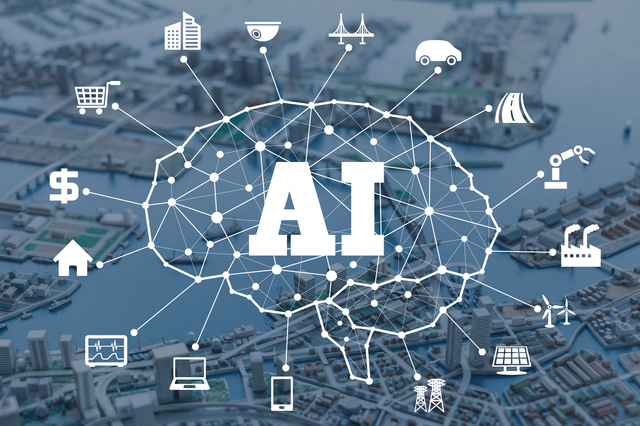企業を取り巻く社会環境の変化により、コーポレートガバナンスを強化することの必要性は年々高まっています。
最近では、企業の不祥事が相次いでおり、その社会的な影響も大きなものとなっています。詳しくは後述しますが『ビッグモーター事件』『ジャニーズ性加害事件』『三栄建築設計事件』などが挙げられます。
著名企業で相次いだ“ガバナンスの欠如”
引用元:ガバナンス欠如の背景に何が【経済コラム】 | NHK | コラム 株・円相場
車にわざと傷をつけて修理し、保険金を不正に請求するなど悪質な不正が横行していたビッグモーター。
その不正を黙認し、顧客保護より自社の利益を優先した損害保険ジャパン。経営トップが多くの未成年者に対し、長期間にわたって性加害を繰り返していたにもかかわらず、何の対策も取らずに放置と隠ぺいに終始したと指摘されたジャニーズ事務所。
そしてプライム上場企業でありながら、創業者の元社長が長年にわたって暴力団員と関わりをもち金銭を供与していたとされる三栄建築設計。
コーポレートガバナンスを強化するために、具体的にどのような取り組みを行えばよいのかイメージが湧かないという企業経営者の方もいらっしゃるかと思います。
コーポレートガバナンスに関する取り組みは、取締役会(=経営陣)のレベルから現場レベルまで、会社組織の隅々まで浸透させることが大切です。この記事では、コーポレートガバナンス強化の必要性や、社内の各機関において求められる取り組み内容などを中心に解説します。
コーポレートガバナンスの必要性と強化するメリットsection
企業が社会的存在としてその役割を十全に果たすためには、「企業の持続的な成長」と「中長期的な企業価値の向上」を実現することが不可欠です。そのためには、コーポレートガバナンスを強化することがさまざまな観点から重要になります。
株主からの信頼を獲得する
コーポレートガバナンスを構成する大切な要素の一つとして、「経営陣と株主の対話」があります。そもそも株主は、会社の実質的な所有者であり、会社経営は株主の信頼の下で行われることが大前提です。
経営陣(あるいは会社全体)が株主の信頼を勝ち取るためには、株主との対話を丁寧に繰り返す姿勢を持つことが重要となります。また、株主に信頼されている企業は、株主総会を円滑に運営できる・取締役が解任されにくいといった特徴があります。そのため、経営陣がフラットな目線で経営判断に注力できるので、適切なリスクテイクを行いやすい点もメリットと言えるでしょう。
ステークホルダーとの協働により企業価値を向上させる
企業は、従業員・顧客・取引先・債権者・地域社会など、さまざまな関係者(ステークホルダー)と関わり合いながら日々のビジネスを行っています。これらのステークホルダーとの協働も、コーポレートガバナンスの要素の一つとされています。
現代の産業は総じて分業制であり、複数の主体が得意分野を持ち寄って協働することにより、大きな価値を生みます。ステークホルダーの協働は、企業の持続的成長を実現するために必要不可欠であり、コーポレートガバナンスを強化してステークホルダーのニーズを適切に吸い上げることが重要です。
不祥事のリスクを低減させる
企業が不祥事を起こしてしまうと、ブランドイメージの毀損や売り上げの減少などが生じ、企業にとって予期せぬ損失を被ることに繋がります。そのため、企業が不祥事のリスクをできる限り回避することは、中長期的な企業価値を向上させる観点からはきわめて重要です。
企業が不祥事リスクを回避するために重要な観点として「コンプライアンス」が知られていますが、コーポレートガバナンスは、コンプライアンスの要素も内包しています。コーポレートガバナンスの考え方では、企業が株主や社会に対して適切な情報開示を行うことにより、企業経営の公正性・透明性を確保することが必要とされているのです。
公正性・透明性の保たれた環境で企業経営を行うことにより、不正行為に対する抑止力が生じ、企業の不祥事リスクが軽減されます。
社会的信用が増し、資金調達が容易になる
コーポレートガバナンスが充実した企業は、中長期的な観点から成長のポテンシャルが高く、不祥事による凋落のリスクも低いとみなされます。このような企業に対しては、銀行や投資家などから見ても、融資や出資を行いやすくなります。
つまり、コーポレートガバナンスを強化することは、企業にとって資金調達を容易にすることを意味し、ひいては事業展開の可能性を広げることにも繋がるのです。
近年コーポレートガバナンスの重要性を高めている3つの要因section
近年の社会情勢の変化によって、コーポレートガバナンスの重要性がますます高まっていると考えられます。
機関投資家や外国人投資家の持ち株比率の上昇
近年の上場企業では、機関投資家や外国人投資家の持ち株比率が上昇し、株主総会における株主の発言機会が増えています。このようないわゆる「モノ言う株主」の割合が増えたことにより、企業の株主に対する説明責任がクローズアップされるようになりました。
そのため企業には、コーポレートガバナンスを充実させ、経営の公正性・透明性を高める努力がますます求められています。
グローバル化によるステークホルダーの増加
インターネットの発展などに伴うグローバル化によって、企業の活動範囲が増えたことにより、ステークホルダーの種類や数も必然的に増えています。多種多様なステークホルダーとの間でいかに協働を実現するかは、国際競争力を高める観点からもきわめて重要です。
そのためには、コーポレートガバナンスの仕組みを整備して、ステークホルダーのニーズを適切に吸い上げることが必要になります。
SNSの発展による、会社に対する社会の監視強化
SNS全盛の現代では、企業の不祥事は、内部リークなどによって以前よりも発覚しやすい環境にあるといえます。また一度企業不祥事が発覚すると、SNSなどを通じて社会全体から一斉に批判を受け、企業のブランドイメージが一挙に失墜してしまうことにもなりかねません。
そのため、コーポレートガバナンスの中でも重要な要素の一つであるコンプライアンスを整備することにより、企業の自浄作用を機能させることの重要性が飛躍的に高まっています。
[2023年]コーポレートガバナンスが問題とされた事例3つと主な問題点を解説section
最近では、企業の不祥事が相次いでおり、その社会的な影響も大きなものとなっています。ここでは、主な事例として3つ取り上げ、問題点などを分析していきます。
ビッグモーター事件
中古車販売等を手掛ける大手のビッグモーターが、ヘッドライトのカバーを割る、ドライバーで車体をひっかく等により顧客の車両を損傷させるなどして保険金を水増し請求していたこと等の不正を行っていた事件です。
2023年6月26日、ビッグモーター社が委嘱した外部の特別調査委員会による調査結果が公表されたことをきっかけに、前記の不正行為のほか、店舗前の街路樹の伐採等のほか、パワハラが横行していたことなど様々な問題が次々に明らかにされました。
ビッグモーター社は、兼重前社長と、息子である副社長を中心とする経営陣でしたが、同年7月26日付けで辞任となっています。その際の記者会見は、社会に大きな波紋を呼びました。
特別調査委員会による報告書(https://www.bigmotor.co.jp/pdf/research-report.pdf)のほか、報道等に表れた主な時系列を整理すると、次の通りです。
| 2022年6月6日 | 損害保険ジャパン株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、及び東京海上日動火災保険株式会社の3社から、連名で、ビッグモーターに対し、自動車修理に関する実態確認の要請文書が提出される。 |
| ビッグモーター社は、現場の経験不足や技術拙劣等が原因であること等を報告→上記3社の納得を得られず | |
| 8月上旬から10月下旬頃 | ビッグモーター社は、関東の4店舗で、保険金請求案件のサンプルテストや従業員ヒアリング等の社内調査を実施 |
| 10月24日から11月上旬頃 | 上記3社に対し不適切な保険金請求事案が確認されたことや、発生原因の分析結果等を報告→なおも上記3社の納得を得られず:調査の客観性、透明性が不十分で網羅性に欠けるとの指摘 |
| 2023年1月30日 | 特別調査委員会を設置 |
| 1月30日から6月20日まで | 特別調査委員会による調査:関係資料の検討、役職員等へのヒアリング、鈑金塗装を所掌する部門や、見積もりや協定を行う工場に配置されていた従業員に対するアンケート実施、サンプルテストによる被害検証 |
| 2月から3月頃 | 滋賀県や熊本県等のビッグモーター社の一部店舗で、車検不正により、車検場としての指定取り消し等を内容とする行政処分 (https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230815-OYTNT50005/) |
| 4月 | ビッグモーター社の元社員とされる人物により、不正整備をレクチャーする様子とみられる動画が拡散される (https://friday.kodansha.co.jp/article/307591) |
| 6月26日 | 特別調査委員会による調査結果の報告書提出 |
| 7月14日 | 損保各社による保険金返還請求 |
| 7月25日 | 兼重宏行前社長らによる記者会見 |
| 7月26日 | 和泉氏が社長に就任。国交省によるヒアリング (https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE262YF0W3A720C2000000/) |
| 7月28日 | 国交省による一斉立ち入り調査 (https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE27A8T0X20C23A7000000/) |
| 8月3日 | 消費者庁が内部通報体制に関する報告要請 (https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE036BP0T00C23A8000000/) |
| 9月1日 | 公正取引委員会が下請代金の不当な減額の疑いについて、調査 (https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE01B4P0R00C23A9000000/) |
| 9月15日 | 警視庁と神奈川県警が、街路樹問題でビッグモーター本社を家宅捜索 |
| 9月19日 | 金融庁が立ち入り調査 (https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB190L80Z10C23A9000000/) |
ビッグモーター事件は、中古車販売業界全体にも影響し、ビッグモーター社以外にも、上場企業での不祥事として、同社に次ぐ業界第2位とされる上場企業であるネクステージや、愛知県を中心とするグッドスピードにおいても、同種の不正事案に関する報道がなされています。(参考:中古車販売「ネクステージ」でも不正疑惑報道…査定に文句言ったら「いきなり56万円アップ」で信用できないとの声
グッドスピードに関しては、不正会計に関する問題も浮き彫りになっています。(参考:グッドスピード、決算で不適切会計か 調査委を設置)
さらには、損保ジャパンに関しても、今回のビッグモーター社による保険金不正請求を認識しながら取引を継続していたことなど、単に「見抜けなかった」以上の問題が浮上しており、金融庁による本格的な調査がなされています。
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2992L0Z20C23A8000000/
- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB190MD0Z10C23A9000000/
そこから、損保業界全体として、保険料の価格調整をめぐる談合に関する問題など、損保業界における市場の歪みも混迷を極めています。(参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB281QV0Y3A920C2000000/)
ジャニーズ事件
日本最大の男性アイドル所属事務所であるジャニーズにおいて、元社長である故ジャニー喜多川氏が、1960年代頃から何十年にもわたり、所属の未成年の男性タレントに対し性加害をしていた事件です。
発端は、2023年3月、イギリス国営放送のBBCのドキュメンタリー番組で、ジャニー氏による性加害問題を取り上げたことがきっかけです。
その後、4月12日、元ジャニーズJr.として活動していた岡本カウアン氏が日本外国特派員協会において記者会見を行い、2012年から16年にかけて15~20回ほど性的被害を受けた旨主張・表明しました。

そして、国連の人権理事会も7月24日から日本で調査を行い、8月4日は記者会見を開き、調査の中だけでも数百人に対する性的加害・虐待が行われる疑惑が明らかになったなどと表明しました。
ジャニーズ事務所側は、当初は事実認定について明らかにしていなかったものの、2023年9月7日に初めて、記者会見において、藤島ジュリー景子前社長がジャニー氏による性加害があった事実を認め謝罪するなどした上で、引責辞任し、新たに東山紀之氏が新社長に就任することとなりました。
被害者に対する補償を尽くしていくため体制を構築している段階とみられますが、株主にはなお前社長の藤島氏がいるなど、従前の体制からの脱却や、社名変更の是非など、問題が山積しています。
| 2023年3月7日 | イギリスBBCでのドキュメンタリー番組において、ジャニー氏による性加害に関する内容が特集される |
| 4月12日 | 元ジャニーズJr.の岡本カウアン氏による記者会見 |
| 4月22日 | ジャニーズ事務所が取引先に説明文書を送付 |
| 5月14日 | 岡本カウアン氏の記者会見を受け、藤島ジュリー景子前社長が動画で謝罪。ジャニー氏による性加害に関する事実認定については、明らかにせず。 |
| 5月16日 | 立憲民主党の議員が、元ジャニーズの男性2人からヒアリング |
| 5月26日 | ジャニーズ事務所が再発防止チームを立ち上げ |
| 6月5日 | 元ジャニーズJr.の橋田氏ほか、岡本氏らが児童虐待防止法改正を求め4万人分の署名を与野党に提出。 |
| 7月14日 | 告発した当事者7人を中心に「ジャニーズ性加害問題当事者の会」を結成 |
| 7月25日 | 国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会の専門家が、当事者からヒアリングを行う |
| 8月4日 | 国連人権理事会が日本記者クラブで記者会見をし、数百人に及ぶ性加害の疑い等に言及し「深く憂慮」といった見解を表明 |
| 9月7日 | ジャニーズ事務所が記者会見を行い、藤島ジュリー前社長が性加害を認め、謝罪など |
| 9月以降 | 広告CMについて、ジャニーズタレントを起用する企業が相次いで契約見直しや、今後の起用見送りなどを表明 |
| 10月2日 | 社名を「SMILE-UP.」とする新会社の設立、ジャニーズ事務所は補償のため存続させた後廃業すること等の新方針を表明。 |
三栄建築設計事件
東京都公安委員会が、2023年6月20日、東証プライム上場の三栄建築設計に対して、東京都の暴力団排除条例に基づき、暴力団に対する利益供与をやめるよう勧告をした事件です。
東証のプライム上場企業への暴力団排除条例に基づく勧告は異例であるとされています。具体的には、三栄建築設計が発注する解体工事代金の一部が、住吉会系暴力団の組長に189万円程度の小切手の形で渡っていたというものです。
小池前社長が会社法に定められる特別背任罪の疑いで家宅捜索を受けるなどしました。
その後、2023年8月15日には、外部調査委員会からの報告書が公表されました。
参考:株式会社三栄建築設計|第三者委員会の調査報告書公表等に関するお知らせ
そして、8月16日、不動産大手のオープンハウスが三栄建築設計の買収を発表し、TOBに向けて動く方針を明らかにし、TOBによる買収期間が9月28日で終了しました。
これれらの問題点の分析
いずれも業界でトップクラスの企業、国際社会含めて影響度が高い企業、上場企業での大きな不祥事であるため、大規模な波紋を呼ぶものとなっています。
共通点として考えられるポイントを3つ挙げて、検討していきます。
経営陣に対して意見できないような企業風土
ビッグモーター事件では、特に「経営陣に盲従し、忖度する歪な企業風土」とまで表現されましたが、トップダウンで権威主義的な経営体制により、現場の社員が目の前の事象や行動に対して合理的に判断することができないような環境にあったと考えられます。
ルール以上に企業の体制や文化が人の行動に影響を与えた結果、社会的なルールに逸脱していることが明らかであっても、それが見えなくなるような空気感が形成され、行動が歪められたといえるでしょう。
ジャニーズ事件の例でも、いわゆるグルーミングという手法により、ジャニー氏がアイドル事業を通じて自己の性的欲求を満たすフィールドを形成していたほか、周囲もやむを得ず、あるいは意図的にそれを黙殺する不文律が形成され、仕組み・習慣化されるに至ったものと考えられます。
これらには、同族経営という点が要因となっているとも考えられますが、より大きな枠組みとしては、次に述べるステークホルダーの利害関係が影響していると考えられます。
ステークホルダー間の依存的な利害関係
これは、特に不正の温床になっている部分との間で、本来同調関係にない(あるべきではない)はずのステークホルダーが、経済的・構造的な要因によって依存関係に立ってしまうことにあります。
ビッグモーター事件では、事故など様々な要因によって修理に出したり、中古車の流通過程で、保険会社側が、本来は対立的な利害関係にあるはずであるところ、緊密な取引上の関係の中でいつしか相互に事業場のメリットをシェアするような関係を構築していった結果、利害を共有するに至ったことが考えられます。
そして、共通の利益形成をする上で、お互いの顧客に分からない水面下で、その依存関係が膨大に蓄積したことで、不正な作り上げていく関係になったものと考えられます。
ジャニーズ事件でも、メディアの原因が大きく指摘されています。なぜなら、今年の動きで初めて浮かび上がった事象ではなく、過去に様々な暴露本や裁判でも、ジャニー氏による性加害が明らかにされていたためです。
メディアが黙殺してきたといっても過言ではないような状況にあったのは、やはり従前のジャニーズ事務所による恩恵を受ける側にあったからであると考えられます。ジャニーズタレントが、様々な企業の広告になったり、莫大なファンの規模からメディアの視聴率を生み出すもので利益の源泉と化していたものであって、メディアの持つ中立性や報道の機能が希薄化していた実情が指摘されます。
三栄建築設計でも、建設業界においては古くから暴力団とのつながりが深いとされるところであり、その関係性の中で事業が構築されてきた文化があることから、暴力団とのつながりを断ち切れなかった側面があると考えられます。
業界の構造的な歪み
1点目や2点目の結果であるともいえますが、業界の構造的な歪みが生じていたと考えられます。
自浄作用や経営に対する監視機能が失われて、不正が常態化したことにより、業界全体から周囲の業界も含めて構造的に、コンプライアンスや事業の仕組みに対する客観的な検証をするような機会が失われるなど、歪みが生じていたといえます。
その大きさが後戻りできない程度に膨れ上がり、外圧もかからない中で、不正が加速していく事態になっていたものであるといえるでしょう。
上場会社に限らず全ての企業でコーポレートガバナンスの強化が重要な理由section
コーポレートガバナンスの重要性は、特に上場企業の場合に強調されることが多いです。しかし非上場企業であっても、コーポレートガバナンスを強化することの意義は、主に以下の理由から急速に高まりつつあります。
将来的な上場を見据えるならば必須
将来的に上場を目指す企業の場合、上場前の業務執行体制についても、上場後の段階で遡って社会からの評価対象になり得ます。たとえ過去の体制不備などであっても、上場後の株価には敏感に反映される可能性が高いので、上場前から襟を正してコーポレートガバナンスに取り組むことが重要です。
ステークホルダーとの協働が必要な点は上場会社と異ならない
株主・従業員・顧客・取引先・債権者・地域社会など、多様なステークホルダーとの協働が必要となる点は、企業の規模にかかわらず同様です。コーポレートガバナンスを充実させ、ステークホルダーからの信頼を得ることで、円滑な協働による持続的な成長が実現する可能性が高まります。
社会の監視は非上場会社にも向けられている
非上場会社であっても、社会規範に違反する経営を行っていることが発覚した場合、やはり社会から批判の対象になってしまいます。特にSNS全盛の現代では、企業イメージが売り上げに与える影響は甚大です。コーポレートガバナンス(特にコンプライアンス)の充実により、不祥事のリスクを低減させることは、非上場会社にとっても重要な課題といえるでしょう。
コーポレートガバナンスを強化する12のチェックポイントsection
コーポレートガバナンスは「企業統治」と訳されることからもわかるように、企業全体を統治するために必要な考え方を含んでいます。言い換えれば、企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するには、コーポレートガバナンスの考え方を全社的に隅々まで浸透させることが大切です。
以下では、コーポレートガバナンスを強化するためのチェックポイントを整理します。
中長期的な経営計画を策定・公表・アップデートする
コーポレートガバナンスの目的は、企業の持続的な成長・中長期的な企業価値の向上を実現する点にあります。取締役会は、経営の中枢を担う機関として、会社としての中長期的なビジョンを内外に示すという大切な役割を果たす必要があります。
また、中長期的な経営計画を策定・公表した後でも、実践を踏まえてその内容をアップデートすることが求められます。特に株主をはじめとするステークホルダーからのフィードバックがあった場合には、その内容を適切に経営計画に反映していくことで、ステークホルダーからの信頼を得ることにも繋がります。
取締役間での相互監視の実効性を高める
取締役による業務執行の公正性・透明性を確保するためには、取締役会の役割である「取締役の職務の執行の監督」(会社法362条2項2号)を実効的に行う必要があります。取締役同士の相互監視を実効的に機能させるためには、社外取締役や、業務を執行しない取締役を積極的に登用・活用するなどの方法が有効です。
取締役の報酬体系を適切に設計する
取締役の報酬体系は、企業の持続的な成長・中長期的な企業価値の向上に向けた適切なインセンティブとなるように設計される必要があります。具体的には、短期的な業績だけでなく、中長期的に会社にとってプラスとなる取り組みを評価できるような業績連動型報酬を導入することが求められます。
現場とのホットラインを開設する
現場レベルの従業員は、会社にとっては日々のオペレーションを支える重要なステークホルダーです。さらに現場レベルの従業員は、日々のオペレーションで多様なステークホルダーと接しています。
より良いコーポレートガバナンスを実現するためには、経営陣が現場レベルの従業員との間で密接にコミュニケーションをとり、多様なステークホルダーのニーズを吸い上げるべきといえるでしょう。
株主との対話を積極的に行う
特に上場会社では、経営陣が株主と接する機会は少ないので、経営陣の側から積極的に株主との対話を求める必要があります。株主との対話を深めることで、株主との信頼関係をベースとした円滑な経営を行うことができるようになります。
また、監査役会(監査役)は、経営陣の暴走を阻止するブレーキとして、コーポレートガバナンスの安定性を高める役割を担っています。
監査権限を能動的・主体的に行使する
監査役会(監査役)は、経営陣と対等な立場で監査を行い、会社内部での不正行為の芽を摘むことが求められます。
その役割を十全に果たすためには、渡された資料に目を通すだけというような受動的な姿勢では不十分です。もし深掘りすべきポイントがあれば、監査役会(監査役)が自ら能動的に会社に対して追加の資料を要求し、実効性のある監査を行う必要があります。
そのうえで、監査役会(監査役)が独立した立場から、経営陣に対して能動的・主体的に意見を述べることが重要です。
社外取締役と連携する
社外取締役は取締役の中でも会社からの独立性が高く、監督機能を期待されている部分も大きいことから、監査役の職務と親和性があります。監査役会が必要に応じて社外取締役と連携を行うことで、取締役会に関する情報をタイムリーに得ることができ、実効的な監査に繋がるでしょう。
少数株主の意見を尊重する
株主総会決議には、原則として多数決の論理が採用されているものの、それは少数株主の意見は無視して良いということを意味しません。むしろ、少数株主の建設的な意見の中にこそ、よりよい会社経営を行うためのヒントが詰まっていることが多いといえます。
したがって株主総会では、多数決の論理で押し切る議事進行をするのではなく、少数株主が持っている考え方の背景などをよく理解して積極的に対話を行うことが大切です。
多様な株主に配慮した運営を行う
外国人投資家などの場合、日本語による説明資料を理解することが難しいこともあります。また、海外在住であるなど、株主総会への出席が物理的に難しい株主も存在します。このように幅広い属性の株主がいることを踏まえて、会社としては、できるだけ多くの株主に権利行使の機会を確保すべきといえます。
たとえば英訳資料を準備したり、書面投票・電子投票を認めたりすることが、このような株主の権利行使の機会確保に繋がるでしょう。
わかりやすい言葉・論理で株主に説明する
経営陣が株主総会での説明・回答などを行う際には、株主の疑問に対して率直に答えることが「対話」の促進に繋がります。そのため経営陣は、過度に婉曲的な言い回しを用いるのではなく、わかりやすい言葉・論理による説明を株主に対して行うべきです。
取締役会などの上層部がコーポレートガバナンスに関する意識を高めても、その考え方が現場の従業員レベルまで浸透しなければ、真の意味での企業統治は成立しません。特に、現場の従業員レベルにおいては、コンプライアンスを徹底することが重要なポイントになります。
コンプライアンス意識を浸透させる
会社におけるコンプライアンス違反は、日々のオペレーションの中で生じることが多いです。そのため、コーポレートガバナンスの重要な要素であるコンプライアンスを徹底するには、現場レベルにコンプライアンス意識を徹底させる必要があります。たとえばOJT(On the Job Training、実地研修)やコンプライアンス研修を通じて、従業員一人一人にコンプライアンス意識を徹底させるような取り組みを、全社的に推進すべきでしょう。
内部通報制度を整備する
社内で行われている違法行為を放置すると、企業にとって潜在的なレピュテーションリスク等が増大します。現場レベルで違法行為の芽を摘むためには、「内部通報制度」を充実させることが有効です。特に弁護士などを活用して社外窓口を設置すれば、従業員による通報の心理的なハードルが下がり、結果として現場レベルでのコンプライアンスを実効的に機能させることに繋がります。
内部通報制度に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。
(参考:「内部通報窓口を弁護士に任せる5つのメリットと弁護士に依頼した際の実務とは」(労働問題弁護士ナビ))
コーポレートガバナンス強化の推進に必要な人材とは?section
コーポレートガバナンスの強化のために、どのような人材が必要でしょうか。ここでは3つ紹介していきます。
外部・社外の人材
まずは、社内に関わりの薄い社外人材が挙げられます。前記のような大規模な企業の不祥事の例にみられるように、大きな要因となったのは、外圧がなく経営に対する監視機能が存在せず、あるいは維持できる程度の基盤が備わっていなかったことにあると考えられます。
そのため、社外の立場から、独立性が確保される中で、客観的に経営を監視できる人材が不可欠であるといえます。
社外というのは、より根本的には、業界の慣習や仕組みの中にいない、あるいは利害関係が及ばない立場です。特殊な人間関係の中だけで大きな不祥事が起こるのではなく、前記のように、むしろ大きな仕組みや構造の中で形成される依存的な利害関係によって、監視機能が弱まります。
そのため、そうした仕組みや利害関係が及ばない立場の人材を、コーポレートガバナンス推進の人材として据えることがポイントになります。

バックオフィスのマネジメント経験のある人材
実際のガバナンス上のオペレーション構築や運用に対する経験という意味では、バックオフィスのマネジメント経験のある人材が有益であると考えられます。
コーポレートガバナンスは、より体系化され、仕組み化されています。そして、それを実効的に運用していくにあたっては、業界ごとの運用ルールや慣習、様々な仕組みの中でオペレーションを運用してきた経験が重要になってきます。
弁護士などの法律や会計士等の専門家
そして、弁護士、公認会計士などの専門人材も重要なポイントです。コーポレートガバナンスに関する体系的な仕組みを構築運用していく上で、高度な知識や経験が必要です。
バックオフィスのマネジメント経験がある場合でも、それが部分的であったり、特定の業界に集中していることにより、汎用的なノウハウとして蓄積されていないことも考えられます。
専門人材であれば、ある程度広範な業界との関りや、汎用的なスキルとして持ち合わせている人材も多くいます。そのため、専門性の高い人材の中で、コーポレートガバナンスに知見を有するかどうかという点も、ポイントの1つです。


ガバナンス強化を考えるうえで参考になるコーポレートガバナンス・コード(企業統治)section
東証の上場会社向けの企業統治に関するガイドラインとして、「コーポレートガバナンス・コード」が策定されています。
(参考:「コーポレートガバナンス・コード」(株式会社東京証券取引所))
コーポレートガバナンス・コードは、以下の5つの基本原則と、それぞれの基本原則を補充する原則・補充原則から成り立っています。
コーポレートガバナンス・コード
5つの基本原則クション
- 株主の権利・平等性の確保
- 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
- 適切な情報開示と透明性の確保
- 取締役会等の責務
- 株主との対話
コーポレートガバナンス・コードは上場会社向けではあるものの、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や具体的な取り組みなどについて、非上場会社にとっても参考になる部分が多いです。
これからコーポレートガバナンスの体制整備を行う企業は、コーポレートガバナンス・コードの内容を一定の参考にするとよいでしょう。

コーポレートガバナンスの強化は弁護士に相談をsection
今後上場を目指す、または中長期的な企業価値を高めたいなどの理由からコーポレートガバナンスを強化しようとする場合は、弁護士のアドバイスを受けながら対応に着手することが有益です。
企業法務に精通した弁護士であれば、コーポレートガバナンス強化に関する社内の体制整備や、株主やステークホルダーとの対話に際しての留意点などについてアドバイスを提供することができます。また弁護士は、社外取締役・監査役・内部通報制度の社外窓口など、さまざまな立場から企業のコーポレートガバナンスを支える主体としてもコミットすることも可能です。
コーポレートガバナンスを実効的に機能させるためには、弁護士の有する法的知見を会社経営に取り入れるメリットは大きいといえます。これからコーポレートガバナンスの強化を目指す企業経営者・担当者の方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
コーポレートガバナンスの強化に社外役員の選任を
社外役員選任サービス『ExE(エグゼ)』は、上場準備中のスタートアップ、コーポレートガバナンス・コードを見据えた体制構築などに長けた、専門性の高い弁護士をご紹介するサービスです。事業成長とガバナンス確保両立の為に、弁護士を起用したい企業様を支援します。
まとめ
コーポレートガバナンスを強化すると、株主などのステークホルダーや社会からの信頼を獲得することで、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促すことに繋がります。
コーポレートガバナンスを適切に強化するためには、コンプライアンスをはじめとした各機関における取り組みについて、弁護士のアドバイスを受けることが有効です。コーポレートガバナンスを強化するための方策を練っている企業経営者・担当者の方は、一度弁護士のアドバイスを求めてみると、新たな発見が得られるかもしれません。